![]()
|
No.1 生活困窮者支援とメンタルヘルス ―NPO法人ほっとプラスへの相談事例から考察する― |
NPO法人ほっとプラス代表理事 藤田孝典
30歳代の女性の事例から〜薬物依存症に対応する社会資源の不足〜
また、別の30歳代の女性は、同じように刑務所を出所し、友人に連れられて相談に来られた。女性は、シンナーや覚醒剤の常習的な使用者で、ストレスや不安を感じると薬物に手を出してしまうという。幼少期から両親が不仲で、家庭内暴力や虐待が日常的にある家庭環境で生きてきたことを話してくれた。家族や友人など、これまで親身になって話を聞いてくれる人が少なく、様々なストレスを感じたときには、一時的に開放感を味わうために薬物を使用してしまったそうである。女性自身も現状から抜け出したい希望を持ってい たが、一人では止めつづける自信がないという。適切な支援がなければ、再犯をしてしまう可能性もあった。しかし、女性だけで薬物を止めるために適切な医療施設やプログラムを探し、受け入れ先を見つけることは困難である。複雑な事情や様々な生活課題がある相談者ほど自分自身では、医療機関や自助グループへつながることができていない状況がある。そのため、関係機関に連絡を行い、薬物依存症者の自助グループへ同行し、精神科受診など継続的な支援を行っていくこととした。
生活困窮者に関わるソーシャルワーカーの持つべき視座
多くの相談者が現状から抜け出したいと希望し、相談に来られる。相談者に共通するものは、現状から抜け出すための情報が足りないこと、または情報があったとしても必要な支援に結びつくために交渉や折衝が必要で、それが一人では困難な局面にあるといえる。ソーシャルワーカーは、一人ひとりに何が必要で、どのような関係機関と連携すれば、現状を打開できるか一緒に考えることが必要である。相談者の状況をアセスメントし、情報を統合・分析し、関係機関と支援ネットワークを構築していくことが必要な状態であるといえる。そして、相談者の抱えるメンタルヘルスに丁寧に向き合って、解決策を模索していくことが重要である。
一見すると、簡単に薬物に手を出してしまう相談者、短期間で仕事を転々として怠け者として見られてしまう相談者、すぐに感情を出してしまう相談者、コミュニケーションが上手くとれずに孤立してしまう相談者がいる。しかし、そのような行動の背景には、メンタルヘルスの課題があり、アセスメントに依拠した相談支援が的確に導入されていない可能性がある。大事なことは、本人のパーソナリティや自己責任として事象を捉えるのではなく、どのような支援があれば生活環境が改善し、不安や生活課題が解消するのか相談者と共に試行錯誤していくことであろう。
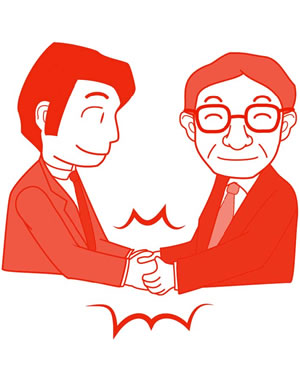
1.NPO法人ほっとプラスの相談支援現場/相談者に見られるメンタルヘルスの課題
2.20歳代の男性の事例から〜仕事先を転々としてしまう若者〜/50歳代の男性の事例から〜刑務所を出所してきた人に対する支援〜
3.30歳代の女性の事例から〜薬物依存症に対応する社会資源の不足〜/生活困窮者に関わるソーシャルワーカーの持つべき視座
4.『戦後の浮浪者の精神医学的研究』から/まとめ