![]()
|
No.3 共働き家族とメンタルヘルス
|
東京都立大学人文学部 稲葉 昭英
2 有配偶女性の就労とメンタルヘルス
結婚している(有配偶)女性の就労が女性自身に及ぼす効果については、2つの異なった仮説があります。ひとつは、メンタルヘルスに悪影響が生じる、という役割過重仮説です。この仮説は、女性は家事や育児・介護を担当しなければならないことが多いため、職業をもつと二重負担に苦しむ、このために心理的に良くない結果が生じると考えます。この仮説が正しいなら、共働き女性よりも専業主婦の方が心理状態がよいことになります。
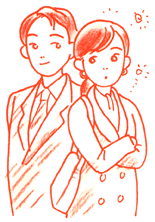 もう一つの仮説は、就労によって女性のメンタルヘルスは改善されるという仮説で、役割展開仮説とよばれます。この仮説は、人は職業役割を持つことで自分自身の存在感や社会的な有能性を感じることができ、心理的によい影響が生じると考えます。さらに夫への経済的な依存が小さくなるため、夫婦関係が対等になり、女性にとって望ましい状態が実現すると主張します。逆に専業主婦は、自分自身の存在感や有能性を実感できる場が限定され、夫への経済的依存が大きいために、夫婦関係において従属的な立場になりやすく、心理的に不満や不安などを経験しやすい、ということになります。
もう一つの仮説は、就労によって女性のメンタルヘルスは改善されるという仮説で、役割展開仮説とよばれます。この仮説は、人は職業役割を持つことで自分自身の存在感や社会的な有能性を感じることができ、心理的によい影響が生じると考えます。さらに夫への経済的な依存が小さくなるため、夫婦関係が対等になり、女性にとって望ましい状態が実現すると主張します。逆に専業主婦は、自分自身の存在感や有能性を実感できる場が限定され、夫への経済的依存が大きいために、夫婦関係において従属的な立場になりやすく、心理的に不満や不安などを経験しやすい、ということになります。
役割過重仮説は、夫が家事や育児に参加しないほど成立すると予想できます。そして、家事や育児・介護の総量が多いときほど、言い換えれば育児や介護が必要な時期ほど、また職業上の役割が多い人ほど、つまり臨時雇より常勤に、パートタイムよりフルタイムに成立しやすいと予測できます。一方、役割展開仮説は、女性が仕事を通じて得られるものが多いほど成立することが予想されます。 では、データはどちらを支持するのでしょうか?
 筆者は、1993年に東京都調布市から得られた代表性のあるデータを用いて、この分析を行っています。回答者は夫をもつ30代の女性ですが、6歳以下の子どもをもつ女性を専業主婦、自営業、臨時雇、常勤の4つに分類し、質問紙調査によってディストレス(うつ、不安、身体的疲労などによって測定される、心理的に望ましくない状態のこと。メンタルヘルスの代表的な指標)を比較したところ、意外なことに、4つのグループのディストレスの平均値に統計的な差異はありませんでした。拍子抜けするようですが、役割過重仮説も、役割展開仮説も、どちらも支持されなかったわけです。
筆者は、1993年に東京都調布市から得られた代表性のあるデータを用いて、この分析を行っています。回答者は夫をもつ30代の女性ですが、6歳以下の子どもをもつ女性を専業主婦、自営業、臨時雇、常勤の4つに分類し、質問紙調査によってディストレス(うつ、不安、身体的疲労などによって測定される、心理的に望ましくない状態のこと。メンタルヘルスの代表的な指標)を比較したところ、意外なことに、4つのグループのディストレスの平均値に統計的な差異はありませんでした。拍子抜けするようですが、役割過重仮説も、役割展開仮説も、どちらも支持されなかったわけです。
平均値だけ見ると、常勤の女性のディストレスはもっとも低いものでした。他のデータでも、乳幼児を抱えた時期に常勤の女性に高いディストレスが経験されていることを報告するものは筆者の知る限りありません。少なくとも、役割過重仮説は成立していないことになります。共働きの妻をもつ夫が、家事や育児に参加し、妻に協力的であるためにこうした結果が生じたのでしょうか?
答えは否です。夫の家事・育児参加の程度は妻の経験するディストレスと統計的に有意味な関連を示しませんでした。早い話が、夫が家事・育児に参加しようと、しまいと、働く妻のディストレスに大きな差異は見られないのです。どういうことなのでしょう?
この謎を解く鍵は親族の存在と機能にあります。6歳以下の子どもをかかえて常勤で仕事をしている女性は、そのほとんどが「いざというときに子どもを預けることのできる親族(具体的には別居している親やきょうだい)」を保有していました。そして、こうした親族を保有していない人はきわめて高いディストレスを経験していました。要は、緊急時に子どもを預けることのできる親族を保有している人が常勤で就労し、こうした条件に恵まれていない人の多くは常勤での就労を断念していたのです。つまり、夫の家事・育児参加よりも親族の利用可能性が、共働き女性にとっては重要な機能を果たしていたのでした。これは、夫婦が家族の基本的な単位である欧米とはきわめて異なった、緊密な親族関係の中に家族が存在するアジアに特有の現象であるようです。
こうして、夫の家事・育児参加が低いにもかかわらず、常勤の女性に役割過重仮説が成立しないことが理解できます。家事や育児を夫婦間で分担するのではなく、親族で分担していたからです。親族が存在しない場合は役割過重仮説が成立し、女性が仕事と家庭の両立に疲弊することになりますが、そもそもこうした選択をしている女性は少数でした。ということは、仕事を続けたいのにこうした親族が存在しないために、就労を断念して専業主婦を選択している女性が少なからず存在する、ということです。
 子育てが一段落すると、緊急時に子どもを預けることのできる親族をもたない女性たちも、再度就労を開始することが多くなります。実は、常勤の女性のディストレスが高くなるのは子どもが6歳以下の時点ではなく、むしろ末子が7歳から12歳くらいまでの時期です。これは、育児や家事を分担してくれる親族を持たないにもかかわらず、常勤で就労する女性がこの時期に多くなり、役割過重が多く経験されることを意味しています。
子育てが一段落すると、緊急時に子どもを預けることのできる親族をもたない女性たちも、再度就労を開始することが多くなります。実は、常勤の女性のディストレスが高くなるのは子どもが6歳以下の時点ではなく、むしろ末子が7歳から12歳くらいまでの時期です。これは、育児や家事を分担してくれる親族を持たないにもかかわらず、常勤で就労する女性がこの時期に多くなり、役割過重が多く経験されることを意味しています。
このように、意外なことですが、未就学の子どもを抱えた時期よりも、小学生の子どもを抱えた時期に共働き女性に役割過重が経験され、好ましくないメンタルヘルスの状態が生じるようです。
1.女性の就業の動向
2.有配偶女性の就労とメンタルヘルス
3.専業主婦のメンタルヘルス
4.共働きの夫のメンタルヘルス