![]()
|
No.2 高齢者と家族
高齢者介護問題を中心として |
安田女子大学文学部人間科学教授 春日キスヨ
1.変わる家族の世代間関係
「あのときが時代の転換期だった」という明確な認識をその時代を生きる人たちはそれほど持っていないことは多いものです。現代日本の家族こそ、後世の人から「世紀末から21世紀初頭ほど家族が変容した時代はなかった」といわれるほどの転換期にあるといってよいでしょう。
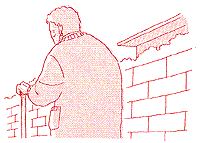 日本人の持つ家族意識は世代別にみると大きく三つに分けられます。大正期生まれまでの戦前の貧しい時代を生き抜いた人たちが持つ「家」制度的家族観。さらに、高度経済成長期に地方から都会に移動し「夫婦中心・子ども中心」こそ理想とする家族観を持ちつつも親によって植え付けられた「家」制度的家族観も残る、昭和一桁生まれから団塊の世代までの人たちが持つ過渡期の家族観。さらに「豊かな社会」であふれるモノに囲まれて育った少子世代が持つ「個」を強調する家族観です。あと15年もすれば明治・大正期生まれに代わり団塊の世代までの人たちが少子世代に介護される時代に移行し、それと共に日本の伝統的家族といわれた家族のありかたも大きく様変わりしていくことでしょう。
日本人の持つ家族意識は世代別にみると大きく三つに分けられます。大正期生まれまでの戦前の貧しい時代を生き抜いた人たちが持つ「家」制度的家族観。さらに、高度経済成長期に地方から都会に移動し「夫婦中心・子ども中心」こそ理想とする家族観を持ちつつも親によって植え付けられた「家」制度的家族観も残る、昭和一桁生まれから団塊の世代までの人たちが持つ過渡期の家族観。さらに「豊かな社会」であふれるモノに囲まれて育った少子世代が持つ「個」を強調する家族観です。あと15年もすれば明治・大正期生まれに代わり団塊の世代までの人たちが少子世代に介護される時代に移行し、それと共に日本の伝統的家族といわれた家族のありかたも大きく様変わりしていくことでしょう。
2000年の「厚生白書」に掲載されていた高齢者と子ども世代との同居率を示す数値はそうした方向性の一つを示唆しています。一例として、健康であっても何らかの見守りケアーを必要とすると思われる85才以上の高齢者の子世代との同居率の変化をあげてみましょう。1975年には80.8%だった同居率が1990年には70.6%、2000年には推計値で63.0%、さらに2010年には54.6%に低下することが予測されています。85才以上の高齢者層でこうですから、これより若年の高齢者層の同居率はもっと低下していくに違いありません。
こうした事実は戦後日本の老親と成人子の世代間関係のあり方が、結婚当初からの「生涯3世代同居」型慣行から、親が高齢になったときもしくは親が倒れて後の「途中同居」型慣行に移行したものの、その慣行も近い将来崩壊し、親が高齢になっても子世代と同居することが少ない欧米型に移行していくことを予測させるものです。また、子世代と同居する比率が欧米ほど低下しなかったとしても、現在「パラサイト・シングル」世代と呼ばれる親と同居する2・30台のシングルの子どもたちが老親の世話をする近未来には、老親と既存の息子家族という組み合わせによって老親とシングルの中高年子という同居世帯が増えていくことでしょう。
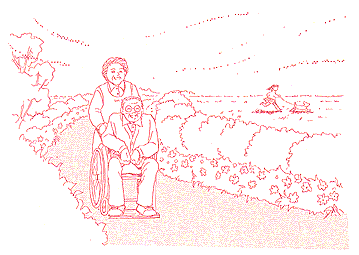
1.変わる家族の世代間関係
2.「嫁」としての介護から「夫の代行者」としての介護へ
3.社会保障制度の成熟と家族関係
4.おわりに