![]()
|
No.2 高齢者と家族
高齢者介護問題を中心として |
安田女子大学文学部人間科学教授 春日キスヨ
3.社会保障制度の成熟と家族関係
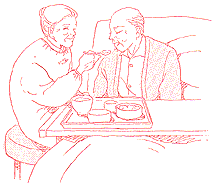 しかし、こうした女性の意識変化は単に女性の側の人権意識の強まりによってのみもたらされたというのではなく、社会保障制度の充実によってもたらされている側面も大きいのです。いくつかの高齢者世代と子世代間の介護をめぐる関係に関する研究は、1980年代半ばに扶養をめぐって大きな変容が生じている事実を指摘しています。家計経済の分析に基づいた研究には、子世代と同居している場合であっても介護が高齢者夫婦間で担われる傾向があり、さらに家計は子世帯家計から独立・分離し、介護費用も子世帯に頼らないで高齢者自身が負担する変化がみられるという報告がいくつかあります。また、家族社会学者らによる研究も、老親と成人子関係において「同居」「扶養」「介護」が分化し、同居型自宅介護が主であり、介護者は配偶者か娘か嫁という形で女性であることが多いが、費用は親世代が用意して子供の負担にならない、つまり経済的扶養と介護とは別問題という新しい枠組みが団塊の世代から生じてきている事実を指摘しています(山田昌弘ほか:『未婚か社会の親子関係』、有斐閣)。
しかし、こうした女性の意識変化は単に女性の側の人権意識の強まりによってのみもたらされたというのではなく、社会保障制度の充実によってもたらされている側面も大きいのです。いくつかの高齢者世代と子世代間の介護をめぐる関係に関する研究は、1980年代半ばに扶養をめぐって大きな変容が生じている事実を指摘しています。家計経済の分析に基づいた研究には、子世代と同居している場合であっても介護が高齢者夫婦間で担われる傾向があり、さらに家計は子世帯家計から独立・分離し、介護費用も子世帯に頼らないで高齢者自身が負担する変化がみられるという報告がいくつかあります。また、家族社会学者らによる研究も、老親と成人子関係において「同居」「扶養」「介護」が分化し、同居型自宅介護が主であり、介護者は配偶者か娘か嫁という形で女性であることが多いが、費用は親世代が用意して子供の負担にならない、つまり経済的扶養と介護とは別問題という新しい枠組みが団塊の世代から生じてきている事実を指摘しています(山田昌弘ほか:『未婚か社会の親子関係』、有斐閣)。
このように年金制度の充実によって高齢者が経済的に自立することは、従来の親に対する扶養義務から息子たちが解放されていくことを意味しています。しかし、そのことは一方で、息子の妻や娘といった介護を実質的に担う個人の介護貢献度を際だたせ、そのことが従来の息子優先の相続制度への不満、などを生み出していく面もあるのです。そして、さらには介護を担った本人の働きが評価されないような介護など引き受けたくないといった形の介護拒否などを生み出し、そうしたことが介護をめぐる家族葛藤を深くしている側面も現実には多いのです。
このように老親世代に対する社会保証体制が整っていくと、それとともに子世代が親世代に対して持っていた従来の扶養観念も徐々に大きく変わっていきます。各種世論調査結果などもこうした扶養意識の変化を報告しています。
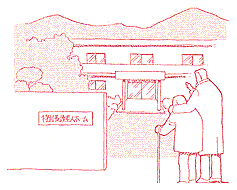 たとえば、『第22回家族計画世論調査』(毎日新聞社人口問題調査会、1994)は、「老親扶養意識」において「子どもとして当たり前の義務」「よい習慣」という考えを肯定する人の割合が過半数を占めていたものが、80年代半ばを境にして急減し、かわって「施設・制度の不備ゆえやむをえない」という考えを肯定する人が増大している事実を指摘しています。
たとえば、『第22回家族計画世論調査』(毎日新聞社人口問題調査会、1994)は、「老親扶養意識」において「子どもとして当たり前の義務」「よい習慣」という考えを肯定する人の割合が過半数を占めていたものが、80年代半ばを境にして急減し、かわって「施設・制度の不備ゆえやむをえない」という考えを肯定する人が増大している事実を指摘しています。
1.変わる家族の世代間関係
2.「嫁」としての介護から「夫の代行者」としての介護へ
3.社会保障制度の成熟と家族関係
4.おわりに