![]()
|
No.3 「生きる力」の基盤である
豊かな心を育てる具体的手立てを! |
順天堂大学大学院教授 大津一義
イラスト 加藤 都巳
3.心の健康づくり
1)よりよい人間関係育成のための意図的計画的環境づくり
心の健康づくりは、よりよい人間関係の育成と密接に関連しているので、どのような人間関係ないし集団の場や機会を設定するかがカギとなる。人間関係は横軸としての同年齢者と縦軸としての異年齢者(年長者及び年少者)とが相互に関連しながら形成されていく。同年齢者同士では自立心、年長者との交わりでは信頼・満足感、年少者との交わりでは、思いやり・自律・自己統制力(セルフコントロール)が育まれることから、同質集団で交わる機会の多い学校生活に下級生や地域の人々、家族などによる異質集団との交流の機会を意図的積極的に増やすようにする必要がある。
2)科学的根拠に基づく心の健康教育プログラムの開発
子供の心の健康づくりの本命は、子ども自身が主体的に心の問題に対応できる自己教育力を培うことにあり、これを可能にする心の健康教育プログラムを開発する必要がある。
(1)心の健康を測定可能な概念として定義する
そのためには、これまでのような徳目的、押しつけ的指導や経験則に終始しないよう、心の健康を測定可能な概念として操作的に定義し、これに基づいて、プログラムの内的要件である目的・目標、学習指導内容(教材含む)、学習指導法、評価の仕方を決定する必要がある。人が健康な心を育むための行動(思いやり行動等)をとる際には自己概念を内的基準枠にしている。この自己概念についての善し悪しの評価結果として生じるのがセルフエスティーム(SE)である。このSEは人と人との関係の中で生じ育まれることから、SEを改善するには「自分自身との関係」と「他者との関係」、これらの相互関係から生じる「行動との関係」の3領域からのアプローチが必要である。このチェック票も開発されており、これら3側面の測定・評価が可能であるし、自己効力感の4つのアプローチ、即ち、遂行行動の成功体験、代理的経験、言語的支援、情動的状態の抑制やライフスキル学習によってSEを高めることも可能である。また、SEは自尊感情などと訳されているが、SEの高い人は、安心感や存在感、自己効力感(セルフエフィカンシー、有能感、自信)が高いので、自分自身を肯定的に受け入れることができ、その結果、他者をも肯定的に受容できるので自他肯定感と称すことにしている。交流分析論に基づけば、心が健康な人とは、この自他肯定の人生態度(I am OK, You are OK)を有し自己実現を目指している人であり、交流分析のエゴグラムチェックリストによって測定・評価できトレーニングも可能である。
(2)ライフスキル教育の導入
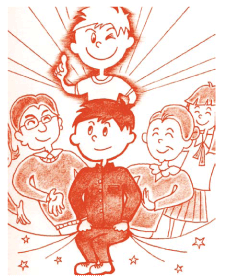 WHO精神健康部は、自分に自信がない、自分の気持ちをうまく伝えられない、他人を思いやることができない等の不適応行動は詰まるところ、心理的社会的要因によって引き起こされているとして、これに対処するためのライフスキル(日常生活の諸問題に適切かつ積極的に対処し行動するために必要な心理的社会的能力)を5組10種類、即ち(①-1意志決定スキル・①-2問題解決S、②-1創造的思考S・②-2批判的思考S、③-1アサーティブコミュニケーションS・③-2対人関係S、④-1自己認識S・④-2共感S、⑤-1情動抑制S・⑤-2ストレスマネジメントS)を開発した。これらのライフスキルに匹敵するスキルは、従前は、言わば生活の知恵やコツとして、親から子どもへの躾などを通して無意図的体験的に伝承されてきた。しかし、人間関係が希薄化するに伴って伝承の機会が極めて少なくなってきている状況の中で、「思いやりのある人になりなさい」、「人に分かるように話しなさい」などと言われても、どうしたらよいかが身についていないので分からないし、だからといって偶然に身に付くのを待っているわけにもいかない。家庭や地域の教育力が低下してきている今日では、その教育力を高める一環として、学校や家庭や地域が一体となってライフスキル形成への本格的な取り組みをしていかなければならない。筆者らもこれまで、現場教師の要請が高く、しかもSEの「行動との関係」改善のための意志決定スキル、「他者との関係」改善のためのアサーティブコミュニケーション(自己表現)スキル、「自分自身との関係」改善のための自己認識スキルを形成するために、授業の成否の70%を決めるといわれる教材として表1、2、3に示したワークシートを開発した。
WHO精神健康部は、自分に自信がない、自分の気持ちをうまく伝えられない、他人を思いやることができない等の不適応行動は詰まるところ、心理的社会的要因によって引き起こされているとして、これに対処するためのライフスキル(日常生活の諸問題に適切かつ積極的に対処し行動するために必要な心理的社会的能力)を5組10種類、即ち(①-1意志決定スキル・①-2問題解決S、②-1創造的思考S・②-2批判的思考S、③-1アサーティブコミュニケーションS・③-2対人関係S、④-1自己認識S・④-2共感S、⑤-1情動抑制S・⑤-2ストレスマネジメントS)を開発した。これらのライフスキルに匹敵するスキルは、従前は、言わば生活の知恵やコツとして、親から子どもへの躾などを通して無意図的体験的に伝承されてきた。しかし、人間関係が希薄化するに伴って伝承の機会が極めて少なくなってきている状況の中で、「思いやりのある人になりなさい」、「人に分かるように話しなさい」などと言われても、どうしたらよいかが身についていないので分からないし、だからといって偶然に身に付くのを待っているわけにもいかない。家庭や地域の教育力が低下してきている今日では、その教育力を高める一環として、学校や家庭や地域が一体となってライフスキル形成への本格的な取り組みをしていかなければならない。筆者らもこれまで、現場教師の要請が高く、しかもSEの「行動との関係」改善のための意志決定スキル、「他者との関係」改善のためのアサーティブコミュニケーション(自己表現)スキル、「自分自身との関係」改善のための自己認識スキルを形成するために、授業の成否の70%を決めるといわれる教材として表1、2、3に示したワークシートを開発した。
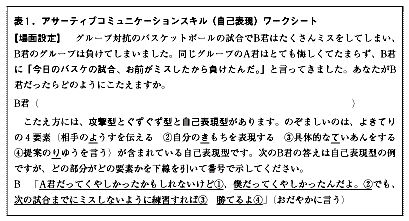
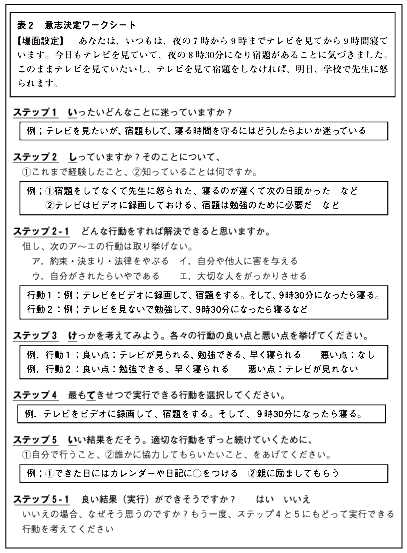
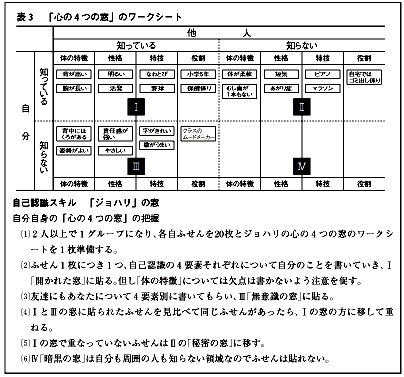
(3)プリシード・プロシードモデルに基づく「QOLで始まりQOLで終わる健康教育」
PPモデルはグリーン(Green.L.W.)らが開発したモデルで、健康教育のねらいは、健康に関する知識・認識、情意と行動、ライフスキルを形成し→健康行動の変容を促し→健康状態を改善して→QOLを高めることにあるとしている。健康教育の企画立案に当たっては、その逆の流れ、即ち、QOL要因の分析(どんなことに困っていて、どうしたいと思っているか)とその目的設定→健康状態要因→ライフスタイル(健康行動の変容を含む)要因→知識・認識、情意、行動、ライフスキル要因の順に、それぞれ前の段階に影響を及ぼす因子を明らかにして目標が設定される。この流れのうちの「健康行動の変容」は健康教育特有の目標であり、これを中心にして見ると、前提要因(知識、態度)、強化要因(行動後の満足感、自分にとって重要な人)、実現可能要因(ライフスキル、専門家、利用しやすい施設など)、ライフスタイル要因(生活習慣など)、生活環境要因、健康状態要因、QOL要因の7つが関与している。そして、健康教育の介入効果は各段階で設定された目標と最終的にはQOLの向上が達成されたか否かで評価される。従って、PPモデルに基づく健康教育は従来のような知識で始まり知識で終わるのではなく、QOLで始まりQOLで終わる学習指導過程を経ることになる。知識はQOL向上の手段であるし、さらにWHOも指摘しているように健康状態もQOL向上の資源・手段なのである。この立場から、心の健康教育のプログラム開発も進める必要がある。例えば、QOL要因として自信をつけたいという場合は、実現可能要因のライフスキル因子としてアサーティブコミュニィケーションスキルと前提要因(態度)として自己効力感を培い、強化要因(重要な人)としてピアカウンセリングの導入を図るといった具合である。
(4)教科の授業における教科指導と生徒指導(心の健康づくり)の縄型授業の推進
学校の教育機能は教科指導と生徒指導に大別される。豊かな人間関係づくりや規範意識の向上等に向けた指導は生徒指導を中心に行われることになっているが、実情は一方的押しつけ的指導に終始しているきらいがある。教科指導も、教科の知識の一方的教授に終始し、学習意欲のわかない不健康な状況にある。そこで、筆者は、ヘルシースクール推進校において、教科の授業に生徒指導を取り込み、健康観察の徹底や健康に関する指導をしたり、学習集団づくりとして、授業の流れに応じて、協調性を高めるための「一体感づくり(よりどころづくり)」→自立性を高めるための「仕組みづくり」→主体性を高めるための「値うちづくり」をしたりなどして、心の健康づくりを進めその効果を挙げている。