![]()
|
No.4 ひきこもり化をもたらす学校教育
|
明星大学大学院人文学研究科長・教授高塚雄介
イラスト こんのあやこ
1.ひきこもりの実態から見えてくるもの
内閣府が実施した調査により、わが国における若者のひきこもりの実態がほぼ明らかになってきた。15歳以上39歳未満を対象としたこの調査により、その数は全国推定で約70万人、さらにその周辺に150万人にのぼる「ひきこもり親和群」と呼ぶべき存在が明らかになっている。一部マスコミなどはこれをひきこもり予備軍と称して取り上げているが、調査を実施した立場では、これを予備軍としてはとらえてはいない。もちろん、いずれひきこもりになる者たちが含まれている可能性は否定できないのだが、親和群に対しての検討すべき課題は他にあると思っている。親和群は女性が多いこと(ひきこもりは2:1で男性が多いのだが、その比率は親和群において逆転している)や、同じような過去体験、意識面でひきこもりとの共通性が高いにも関わらず、ひきこもりにはならないでいる理由等を究明することで、もしかするとひきこもりの予防策が見つかる可能性があると思っている。
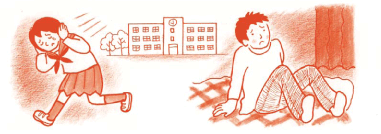
この内閣府の調査結果とは別に厚生労働省の研究班が独自の調査結果として「ひきこもり」には、確定診断になる前の統合失調症や、発達障害などの精神疾患を有するものが相当数いることを提起している。その根拠となっているのは、全国5か所の精神保健センターを訪れたひきこもり相談184名を分析したところそのような知見が得られたとしている。その上で、「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(新ガイドライン)を作成した。わが国の行政機関における「引きこもり対策」は、これをマニュアルとして展開しているところが多い。精神疾患や障害による「ひきこもり」の存在は昔から知られているところであるし、そうした人々に対してきちんと対応することの大切さは否定するものではない。しかし、わが国において増加傾向にある「ひきこもり」の実態とはいささかかけ離れた認識であると言わざるを得ない。
今日の「ひきこもり」の問題と言うのは、精神疾患や障害に起因するとは考えにくい「ひきこもり」状態を呈する若者たちが増加しており、その者たちを「社会的ひきこもり」と称するようになったことから多くの関心が高められた経緯がある。しかしながら、「社会的ひきこもり」という呼び方もまた、多くの混乱を招いている。なぜならば、「社会的ひきこもり」というのは、診断でも症状を現しているものでもなく単なる状態像、現象を示す言葉でしかないと言うところに混乱が生じてしまった。現象としてとらえるならば、精神疾患や障害を有する人たちも社会適応が出来ず、結果的にはひきこもり状態にならざるを得ない人たちが沢山いる。ひきこもり支援をする人たちのところには、そうした疾患や障害を抱える人の家族からも援助を求める人が多く、その支援対象として取り込まざるを得ないという事態が生じているのだ。医療関係者の所にもそうした「ひきこもり状態」を呈する人が多く相談に訪れることから、ひきこもりのとらえ方にある種のバイアスがかかってしまった可能性がある。
本稿はひきこもりについて述べるものではないが、実は内閣府ならびにその前に東京都が実施した同種の実態調査により、ひきこもりがもたらされる背景に、今日の学校教育の在り方が大きく関わっていることが浮かびあがってきている。そのことについてふれてみたい。
1.ひきこもりの実態から見えてくるもの
2.不登校とひきこもりは必ずしもリンクしていない
3.今日の学校教育になじめない子どもたちに注目すべきである