![]()
|
No.4 ひきこもり化をもたらす学校教育
|
明星大学大学院人文学研究科長・教授高塚雄介
イラスト こんのあやこ
2.不登校とひきこもりは必ずしもリンクしていない
社会的ひきこもりという言葉が広められていく初期の頃は、不登校問題とひきこもり問題とは同一の現象であるかのように言われる事が多かった。そして不登校が長期化するにつれ、やがてひきこもり化していく者が多くなるかのようにも考えられた。しかし、実態を調べていくと必ずしもそうではないことがわかった。内閣府調査では不登校からひきこもりになったとする者は全国で11.9%、東京都調査では18.8%にすぎない。過去に不登校を経験したことがあるとする者を加えても、全体の2割程度である。残りの多くは学校を終えてから後、就職活動の躓きや就職した後での挫折からひきこもりになっている。さらに、そのほとんどが人間関係に苦痛を感じていることも明らかになった。人間関係に対する課題は、何も就職してから始まっているわけではないはずだが、学校時代は何とか乗り越えているところに注目してみる必要がある。もう一つの特徴は、「いじめ」にまつわる問題を経験したものが多いことである。いじめが原因で不登校になっていく例というのは多く紹介されているのだが、ひきこもり状態になっている若者たちというのは、必ずしも不登校にはなっていない。これもまた注目すべき点である。さらに「ひきこもり」の若者たちは、勉強についていけないとか、教師とうまくいかなかったということを指摘している。これは何を意味しているのだろうか。それらの体験は不登校になる要因として考えられるのだが、そうならずに学校時代を過ごしている。そして、卒業後に社会に出てから躓くのである。
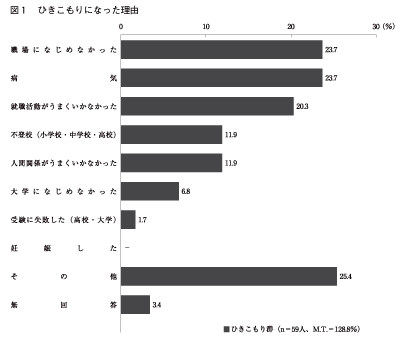
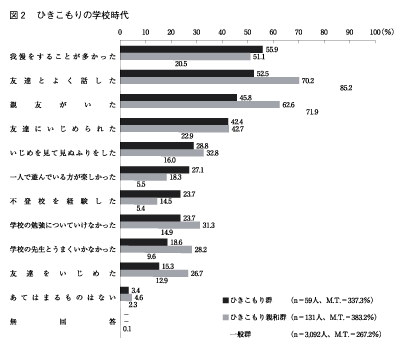
1.ひきこもりの実態から見えてくるもの
2.不登校とひきこもりは必ずしもリンクしていない
3.今日の学校教育になじめない子どもたちに注目すべきである