![]()
|
No.4 ひきこもり化をもたらす学校教育
|
明星大学大学院人文学研究科長・教授高塚雄介
イラスト こんのあやこ
3.今日の学校教育になじめない子どもたちに注目すべきである
 東京都調査では、ひきこもる若者にたいする面接調査も実施しており、その結果も加えて考察していくと次のようなことが浮かび上がってくる。今、学校では「コミュニケーション能力」を高めるということが大きな教育課題となってきている。さらに、自主的に取り組み、自立性を高めるために小集団学習を取り入れるようになっているところが多い。いずれもグローバル化する今日的状況のもとに、中教審などもそのことの大切さを提起したことを受ける形で教育現場では実践されている。アサーショントレーニングであるとか、ディベートを組み合わせた教育はかなり頻繁に行われるようになっている。その成果も多く報告されている。だが、そうしたことに9割型の子どもたちはついていくし、そのことの面白さを味わう子どもも少なくない。しかし、1割程度の子どもたちはそうした学習スタイルについていけないばかりか抵抗を示し、ドロップアウトしていく者も少なくないという現実がともすると見過ごされていく。発達障害を有する子どもたちにはもっとも苦手な課題でもある。しかし、発達障害と認定されれば、今は特別支援教育の対象となり、そこから外れることも認められる。しかし、何の障害を有さなくても、そうしたことの苦手な子どもたちは存在しているのだが、教育現場ではそれは無視されがちであり、それを可能とする子どもたちと同等に評価されていく。苦手な子どもたちは小集団場面においてもほとんど影の薄い存在でしかなく、それがまた他の子どもたちからすると「うざい」存在として、いじめの対象にもなりやすい。昨年末に発生した二つの、子どもの自殺の背景にもそれは浮かび上がってくる。ひとつは給食時間に誰も仲間にいれてもらえず死を選んだ小学生であり、ひとつは「国語の時間のスピーチをやらされるのが嫌だ」とノートに書き遺して死を選んだ中学生である。そうした子どもたちに対して、一律の課題を課すような教育が今の学校現場にはまかり通っている。現代社会、とりわけ企業社会の求める人物像に適応させるようにすることが、本当に教育の課題なのであろうか。「ひきこもり」がもたらされる背景にそうした問題が浮かび上がってくる。
東京都調査では、ひきこもる若者にたいする面接調査も実施しており、その結果も加えて考察していくと次のようなことが浮かび上がってくる。今、学校では「コミュニケーション能力」を高めるということが大きな教育課題となってきている。さらに、自主的に取り組み、自立性を高めるために小集団学習を取り入れるようになっているところが多い。いずれもグローバル化する今日的状況のもとに、中教審などもそのことの大切さを提起したことを受ける形で教育現場では実践されている。アサーショントレーニングであるとか、ディベートを組み合わせた教育はかなり頻繁に行われるようになっている。その成果も多く報告されている。だが、そうしたことに9割型の子どもたちはついていくし、そのことの面白さを味わう子どもも少なくない。しかし、1割程度の子どもたちはそうした学習スタイルについていけないばかりか抵抗を示し、ドロップアウトしていく者も少なくないという現実がともすると見過ごされていく。発達障害を有する子どもたちにはもっとも苦手な課題でもある。しかし、発達障害と認定されれば、今は特別支援教育の対象となり、そこから外れることも認められる。しかし、何の障害を有さなくても、そうしたことの苦手な子どもたちは存在しているのだが、教育現場ではそれは無視されがちであり、それを可能とする子どもたちと同等に評価されていく。苦手な子どもたちは小集団場面においてもほとんど影の薄い存在でしかなく、それがまた他の子どもたちからすると「うざい」存在として、いじめの対象にもなりやすい。昨年末に発生した二つの、子どもの自殺の背景にもそれは浮かび上がってくる。ひとつは給食時間に誰も仲間にいれてもらえず死を選んだ小学生であり、ひとつは「国語の時間のスピーチをやらされるのが嫌だ」とノートに書き遺して死を選んだ中学生である。そうした子どもたちに対して、一律の課題を課すような教育が今の学校現場にはまかり通っている。現代社会、とりわけ企業社会の求める人物像に適応させるようにすることが、本当に教育の課題なのであろうか。「ひきこもり」がもたらされる背景にそうした問題が浮かび上がってくる。
そのようにみていくと、ひきこもりの若者の多くが、いじめにまつわる体験を有し、なおかつ「学校の勉強についていけなかった」「学校の先生とうまくいかなかった」としていることが理解されてくる。しかし、にもかかわらず彼らは必死になって通学し、不登校にはならずに踏みとどまっていることも明らかになった。その理由の一つが、学校時代は「我慢することが多かった」とする者が過半数を超えていることである。彼らは例えつらくても嫌であっても我慢して、卒業にこぎつけたことが推測出来る。さら、面接などでは、彼ら多くはプライドの高い者も少なくないということが示されている。不登校になり、あたかも負け犬のように周囲から見られることもまた、彼らにとっては苦痛となるのであろう。彼らに、SSТのような、精神障害者の社会復帰に向けた行動療法をさせても拒否する者が少なくない。それもまた、彼らの自尊心が許さないもののように思える。とすれば、彼らに対してどのような方策をとれば社会参加の道が開けていくのだろうか。充分に検討してみる必要があろう。ただ、これ以上ひきこもり化をもたらさないようにするための予防策はおぼろげに見えてきた気がする。その中心は学校教育にあると言える。
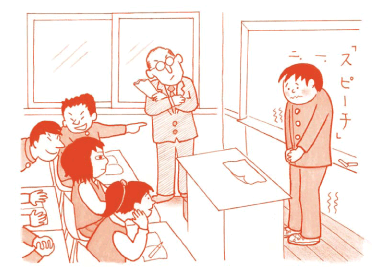
いずれにしても、ひきこもる若者たちの心中と言うのはきわめて複雑であることが理解出来る。彼らを甘ったれた存在と決めつけるわけにはいかないし、単なる社会風潮の産物であるかのようにとらえてはならない。内閣府調査においてもそのようなとらえ方はしていない。むしろ我が国社会がこの半世紀の間、これが正しいと思い込み、一途に進み続けてきたプロセスの中に潜んでいた問題が、ひきこもる若者たちによって露呈したと見るべきではないだろうか。そこには、学校社会の在り方や教育の方向性と言う問題が大きく関わっており、学校メンタルヘルス的な視点から究明されるべきことが多いことを指摘しておかなければならないと考える。
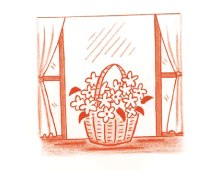
1.ひきこもりの実態から見えてくるもの
2.不登校とひきこもりは必ずしもリンクしていない
3.今日の学校教育になじめない子どもたちに注目すべきである