![]()
|
No.3 勤労者の自殺をめぐる諸問題
|
帝京大学医学部附属溝口病院精神科 張 賢徳
イラスト 清水 徳子
1.はじめに─なぜ自殺予防が必要なのか?
まず始めに、そもそも自殺は防がれるべきものなのかどうかを考えておきたい。なぜなら、この認識がしっかりしていないと、いろいろな理由を挙げて自殺予防を唱えても、本気で取り組もうという気運は高まらないからである。自殺予防のいろいろな理由というのは、例えば、「親からもらった命を粗末にしてはいけない」、「あなたの命はあなただけのものではない」、「遺された人たちの悲しみを考えて」など、身近な人たちからの切実な声がすぐに思い浮かぶ。あるいは、勤労者の自殺ならば、自殺によって発生する経済的な損失や、近年の労災申請件数の増加に代表されるように会社の責任問題というものも、自殺予防の理由に入ってくるだろう。
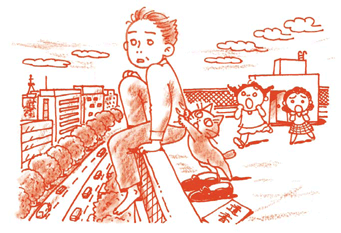
しかし、いろいろな理由を挙げてもなお、根本のところで「自殺は個人の決断だから、周りがとやかく言うものではない」という認識が存在しているのであれば、本気で自殺を防ごうという気運は盛り上がらないのである。この「個人の決断」という言葉には、「理性的な決断」という意味が含まれている。自殺を個人の理性的な決断とする考え方は、自殺を容認する社会風土を生み、自殺予防の理論的な正当性の根幹を揺るがすのである。
理性的な自殺には、例えば、安楽死や尊厳死が含まれる。そのような自殺は確かに存在する。また、日本では、切腹文化の名残のために、自殺は理性的になされるものであると考える社会的風潮が強いように思える。「責任を取って腹を切る」という表現が現代の会話にも用いられ、皆がその意味を理解するという現実がそれを示していると言えるだろう。1998年に年間自殺者数が3万人を突破し、その後「年間自殺者3万人」時代が続いているわけだが、国が自殺予防対策に動き出したのは2000年以降のことである。1997年まで年間2万人以上の人が自殺で亡くなっていたわけだが、ほとんど注目されることもなく、国が予防対策に乗り出すこともなかった。これもまた、自殺を理性的な行為として容認する社会的風土の結果ではなかったかと思う。
「年間自殺者3万人」時代の中で、国が自殺予防対策に取り組むことを表明するため、2006年に自殺対策基本法が施行された。これは画期的なことであり、自殺予防の立場からすれば大変喜ばしい。しかし、その後に起こった某大臣の自殺に対し、「彼は立派なサムライだった」という複数の政治家からの賛辞が報道されたのを聞き、自殺の実態に関する啓発活動がまだまだ不十分であることを痛感させられた。法律ができても、人々の意識が変わらなければ、自殺を本気で防ごうという動きは高まらない。
 自殺は理性的な行為なのか?これこそが、自殺予防運動の根幹に関わる命題なのである。先述のように、安楽死や尊厳死などの理性的な自殺は存在する。このような自殺に対して、「予防すべきだ」と大上段に構える気は筆者にはない。宗教上の問題や遺族の悲しみなど、この種の自殺にも随伴するだろうし、それが自殺を止める理由になりえるだろうが、理性的な本人の意志をどう扱えばいいのだろうか。これは精神医学だけに任されるべき問題ではなく、国民全体で議論されるべきである。
自殺は理性的な行為なのか?これこそが、自殺予防運動の根幹に関わる命題なのである。先述のように、安楽死や尊厳死などの理性的な自殺は存在する。このような自殺に対して、「予防すべきだ」と大上段に構える気は筆者にはない。宗教上の問題や遺族の悲しみなど、この種の自殺にも随伴するだろうし、それが自殺を止める理由になりえるだろうが、理性的な本人の意志をどう扱えばいいのだろうか。これは精神医学だけに任されるべき問題ではなく、国民全体で議論されるべきである。
一方で、諸外国ならびに東京での調査から、自殺者の約90%が自殺時に何らかの精神障害を有する状態にあったことが判明している。最多はうつ病で、50〜70%を占める。精神障害の状態にあることがすなわち完全に理性を失っているとは言えないが、理性が完全に保たれているとも言えない。例えば、うつ病で言うと、認知の歪みと狭窄(極度のマイナス思考や絶望、精神的な意味での「視野」狭窄)が存在し、これが自殺に関与すると考えられるのである。判断の思考過程に病的な影響があるものに対して、「個人の決めたことだから、周りがとやかく言うべきではない」と言えるだろうか。
理性的な自殺は確かに存在するが、その数は圧倒的に少ない。自殺者の大多数は自殺時に何らかの精神障害の状態にあった。そして、程度の差はあれ、理性的とは言えない精神状態にあった。これこそが、自殺は防がれるべき対象だという理論的な根拠なのである。某大臣の最後の精神状態について筆者は知る由もないが、いずれの状態であったにせよ、影響力のある人たちの自殺容認発言を、マスメディアは無分別に流すべきではない。
1.はじめに─なぜ自殺予防が必要なのか?
2.勤労者の自殺の実態─社会経済的な側面
3.勤労者の自殺の実態─精神医学的側面
4.おわりに─自殺予防対策について