![]()
|
No.1 学校メンタルヘルスについて考える
-いま、子どもたちの間になにが起こっているのか- |
中部学院大学大学院教授 吉川武彦
2.「若者たちの自己主張を抑えてきた私たちの社会」という考えから
月刊『児童心理』(臨時増刊・2007年10月)の“子どもたちの暴力“の特集で依頼によってそこに「不登校・引きこもりと家庭内暴力」を寄稿し、「子どもたちが示す『暴力』は自己主張」という視点から、「子どもたちが示す『暴力』には一定のつながりがある」ことをきちんと認識し、そのつながりを明らかにすることから「いま、なにが起こりつつあるかを見据えること」の重要性を主張した。
後述するように、ここでいう「カッコ付きの『暴力』」は、彼らの「自己主張」であるととらえることが重要であり、その自己主張のあり方や方向性はそのものの“こころの成熟”に深く関わるものであると考えているところに私論の根底を置いたものである。さらに、この自己主張としての『暴力』には「外向きの<対社会的(あるいは対他的)に向かう>」と「内向きの<対自的に向かう>」ものとがあるという考えでもある。
この自己主張としての『暴力』の系譜をたどると興味深いものがある。この文脈では思春期・青年期にあるこれらの若者を「青少年たち」と呼ぶこともあるのでご了承願いたい。
表1を見て欲しい。これは1950年頃から今日に至るまで、青少年たちが自己主張としての『暴力』を対他的に示していたものが対他的には示すことができなくなり対自的に示すようになった経過である。不思議なことにほぼ10年ごとに区切ることができる。
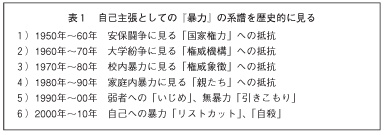
注釈をつけるなら、1950年代も1960年代も自己主張は対社会的な行動として表されてきたが、それが押しつぶされると向かう方向は狭まり対象も次第に小さくなっていったことがわかるし、挙げ句の果ては自己主張としての『暴力』は自分に向けられていくことがわかる。表には示さなかったが拒食行為も対自的自己主張であり、リストカットを含む自傷行為も対自的自己主張である。もちろん自殺も自己を社会的に抹殺しようとする行為であるが、殺人などの重大な犯罪もまた自己を社会的に抹殺しようとする行為と考えることができる。つまり、“年代とともに『暴力』を向ける対象が変わってきた”ことと“『暴力』の質が変わってきた”と考えてまとめたともいえる。
また、見方を変えると表2のように「世代への広がり」としてまとめることができる。
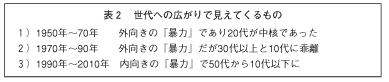
2000年から2010年のまさに“いま”は、自己主張を押さえつけられた青少年たちは「自己への暴力としてのリストカット・自殺」をはじめたからである。近々の報道にもあるように1998年以降3万人の自殺が続いているわが国ではあるが、その中核が40代後半から50代前半の10歳にピークがあったものがそれが明らかに低年齢化してきている。わが国の自殺に関して深い関心を持っている私は、たびたびこうした変化が起こると予想して警告を発してきたがまさに現実化してしまった。これがその下の世代である思春期・青年期に移行するのにあとどれだけの時間がかかるのであろうか。
またさらに、表3のような変化、「地域的な広がり」としてまとめることもできよう。
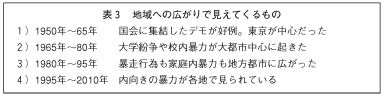
ここではその詳細に触れる余裕はないので先に論を進めることとしたい。
1.いま、子どもたちの問題がかしましい
2.「若者たちの自己主張を抑えてきた私たちの社会」という考えから
3.こころはどう育つのか
4.なぜこころがうまく育たなくなったか