![]()
|
No.1 学校メンタルヘルスについて考える
-いま、子どもたちの間になにが起こっているのか- |
中部学院大学大学院教授 吉川武彦
3.こころはどう育つのか
かねがね私は“こころは「知」「情」「意」と「自分らしさ」で形づくられる三角錐”であると説明してきた。これを図にすれば次頁の図1のようになる。
つまり、真っ直ぐなこころとはこのように三角錐が真っ直ぐに立っているということであると考えてきた。言い換えると「知」の面が大きすぎては三角錐は斜めに立ってしまうわけであり、それは「情」についても「意」についても言える。
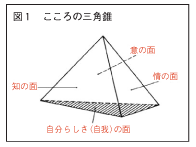 これを具体的にいうと、こころが真っ直ぐであるということは「知」も「情」も「意」もほどほどでいいというわけで、大切なのは底面に比定した「自分らしさ」がしっかりと広がっているということである。「知」「情」「意」のバランスが悪い三角錐は斜めに立つ。底面が狭ければ体積が大きい三角錐もひょろ長く立つだけで不安定である。如何にバランスがとれていても体積が小さい三角錐、つまりこころが小さな人は他人の鼻息でも飛んでしまう。ではこの底面の「自分らしさ」はどのようにして育てたらいいのであろうか。それを示したのが図2である。
これを具体的にいうと、こころが真っ直ぐであるということは「知」も「情」も「意」もほどほどでいいというわけで、大切なのは底面に比定した「自分らしさ」がしっかりと広がっているということである。「知」「情」「意」のバランスが悪い三角錐は斜めに立つ。底面が狭ければ体積が大きい三角錐もひょろ長く立つだけで不安定である。如何にバランスがとれていても体積が小さい三角錐、つまりこころが小さな人は他人の鼻息でも飛んでしまう。ではこの底面の「自分らしさ」はどのようにして育てたらいいのであろうか。それを示したのが図2である。
 誰のこころにも何かしたい“気持ち”が渦巻いている。言い換えると「欲求」が溜まっている。こころのなかにその「欲求」が満ちたときに、外界の「きまり」や「約束」、言い換えれば世間の「規範」とぶつかることになる。意欲がこのように外界のきまりや約束あるいは規範とぶつかり合ってはじめて私たちのこころに“きまり”や“約束”あるいは“規範”が入り込んでくる。ということは、私たちは意欲があって外界とぶつかり合ってこそ規範を引き込むことができるのであって、“外界の「規範」がこころに取り込まれて自分の「規範」となる”といえる。つまり、外界からこころのなかに取り込んだ「欲求」が大きくなって外界の「規範」を引き入れてこそ、自分のこころのなかでその「欲求」と「規範」が闘うことができるのであり、こうして闘いあって折り合いをつけたのが「自分らしさ」だといえる。
誰のこころにも何かしたい“気持ち”が渦巻いている。言い換えると「欲求」が溜まっている。こころのなかにその「欲求」が満ちたときに、外界の「きまり」や「約束」、言い換えれば世間の「規範」とぶつかることになる。意欲がこのように外界のきまりや約束あるいは規範とぶつかり合ってはじめて私たちのこころに“きまり”や“約束”あるいは“規範”が入り込んでくる。ということは、私たちは意欲があって外界とぶつかり合ってこそ規範を引き込むことができるのであって、“外界の「規範」がこころに取り込まれて自分の「規範」となる”といえる。つまり、外界からこころのなかに取り込んだ「欲求」が大きくなって外界の「規範」を引き入れてこそ、自分のこころのなかでその「欲求」と「規範」が闘うことができるのであり、こうして闘いあって折り合いをつけたのが「自分らしさ」だといえる。
欲求が高まっているにもかかわらずそれを誰かが満たしてくれるようなことがあると、外界から規範を引き込むチャンスも生まれない。つまりこころのなかに規範を引き込むこともないわけなので、こころのなかで欲求と規範が葛藤することもない。ということは自分らしさをもつこともないというわけで、こころのなかは空っぽといえる。外界からきまりや約束あるいは規範を引き込むこともなかった人はまさにこころのなかは空っぽであり、何をする意欲もない。これに対してこころのなかにきまりや約束あるいは規範を押し込まれた人は、規範通りには行動できるが自分で何かしたいという意欲は押しつぶされているために自発的には何もできない人となる。命じられればできるが自分から何かをしようという気持ちはないといいわけで、こういう人がいまたくさん私たちの周辺にいる。
さて人間関係は複雑だというが、図3を見てほしい。
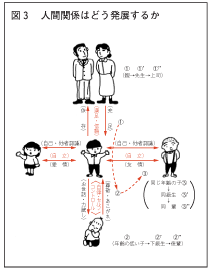 自分よりも年長者との関係①で、これは親であったり幼稚園の先生や保育園の保育士あるいは学校の教師との関係①’であり、長じては上司との関係①”でもある。この関係のなかで人は「信頼」というこころを学ぶ。それは小さい自分や幼いあるいは未熟な自分が上の人から助けてもらうことで人間関係を結ぶのは「信頼」であるとわかる。人を信頼することを学んだものはついで自分よりも年少者のものとつきあう。このつきあいのなかで自分をコントロールする力を獲得する。セルフコントロール(自制心)を学ぶといえる。力を振るいすぎて失敗もするが、自分よりも年下のものから尊敬やあこがれを向けられるようになることで自制心を学ぶ。こうして自制心が育つのだがその自制心をもったものどうしで闘い合うのが次の同年との関係③である。同年のものと闘い合うことで自分の力量を学び、他者の力量を測ることを学ぶのであるが、闘い合いながらも相手の力量を測りあるところで闘いを止めることができるのは、自分よりも下のものとつきあった経験から自分を自制する力をもっているからである。①→②→③→①’→②’→③’→①”→②”→③”→と発展する(図4)。
自分よりも年長者との関係①で、これは親であったり幼稚園の先生や保育園の保育士あるいは学校の教師との関係①’であり、長じては上司との関係①”でもある。この関係のなかで人は「信頼」というこころを学ぶ。それは小さい自分や幼いあるいは未熟な自分が上の人から助けてもらうことで人間関係を結ぶのは「信頼」であるとわかる。人を信頼することを学んだものはついで自分よりも年少者のものとつきあう。このつきあいのなかで自分をコントロールする力を獲得する。セルフコントロール(自制心)を学ぶといえる。力を振るいすぎて失敗もするが、自分よりも年下のものから尊敬やあこがれを向けられるようになることで自制心を学ぶ。こうして自制心が育つのだがその自制心をもったものどうしで闘い合うのが次の同年との関係③である。同年のものと闘い合うことで自分の力量を学び、他者の力量を測ることを学ぶのであるが、闘い合いながらも相手の力量を測りあるところで闘いを止めることができるのは、自分よりも下のものとつきあった経験から自分を自制する力をもっているからである。①→②→③→①’→②’→③’→①”→②”→③”→と発展する(図4)。
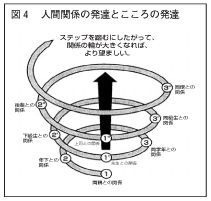 「圧力」に対峙できるこころとは、「自分らしさ」をしっかりともったこころであり、底面の広い三角錐のこころをもっていることが重要であるばかりでなく、これだけのステップを踏んでしっかりとした人間関係のなかでこころを育ててきたものは「こころのつくりがしっかりしている」といえよう。つまり「こころのつくりがしっかりしている」ことが「圧力」にしっかりと対峙する力をもつことができ、自己主張できる=『暴力』を発揮できるといえる。ということは、外界からの「圧力」が大きいから自己主張が押さえつけられてしまい、自己主張もできないと言うのではなく自己主張できるだけのこころに育っていないと言うこともできると言える。それを私は「わが国の近代工業化の進展と子育てや教育が絡み合って生んだもの」だと考えてきた。私たちの国は敗戦後10年を経た1955年以降は、一気に工業化の道を突き進むことになる。近代工業化を推し進めてきたキイワードが「スピード重視/S」「生産性奨励/S」「管理強化/K」「画一化推進/K」の『S/S/K/K』であったがその間にも子4.
「圧力」に対峙できるこころとは、「自分らしさ」をしっかりともったこころであり、底面の広い三角錐のこころをもっていることが重要であるばかりでなく、これだけのステップを踏んでしっかりとした人間関係のなかでこころを育ててきたものは「こころのつくりがしっかりしている」といえよう。つまり「こころのつくりがしっかりしている」ことが「圧力」にしっかりと対峙する力をもつことができ、自己主張できる=『暴力』を発揮できるといえる。ということは、外界からの「圧力」が大きいから自己主張が押さえつけられてしまい、自己主張もできないと言うのではなく自己主張できるだけのこころに育っていないと言うこともできると言える。それを私は「わが国の近代工業化の進展と子育てや教育が絡み合って生んだもの」だと考えてきた。私たちの国は敗戦後10年を経た1955年以降は、一気に工業化の道を突き進むことになる。近代工業化を推し進めてきたキイワードが「スピード重視/S」「生産性奨励/S」「管理強化/K」「画一化推進/K」の『S/S/K/K』であったがその間にも子4.
1.いま、子どもたちの問題がかしましい
2.「若者たちの自己主張を抑えてきた私たちの社会」という考えから
3.こころはどう育つのか
4.なぜこころがうまく育たなくなったか