![]()
|
No.1 学校メンタルヘルスについて考える
-いま、子どもたちの間になにが起こっているのか- |
中部学院大学大学院教授 吉川武彦
4.なぜこころがうまく育たなくなったか
それを私は「わが国の近代工業化の進展と子育てや教育が絡み合って生んだもの」だと考えてきた。私たちの国は敗戦後10年を経た1955年以降は、一気に工業化の道を突き進むことになる。近代工業化を推し進めてきたキイワードが「スピード重視/S」「生産性奨励/S」「管理強化/K」「画一化推進/K」の『S/S/K/K』であったがその間にも子どもを産み育てても来た。近代工業化を推し進めたキイワードとその間に子どもたちにかけてきた言葉を整理すると奇妙な符合が見られる(表4)
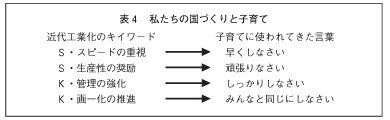
いったいこれで本当に期待するような「いい子」が育ったのであろうか。こうした声かけをして育てた子は、磨きに磨いたぴかぴかの子ですばらしく見えるが、つるつるで丸くてぴかぴかしているだけにまるで“ビー玉”のような人間であり、そこにはどこにもとっかかりがない「ビー玉人間」というべき人間なのではないかというのが私の考えでもある。ビー玉を紙の袋に入れておいてその紙を破けば紙袋に入っていたときは互いにくっつき合っていたはずのビー玉はバラバラになって散ってしまうが、もしもでこぼこの石ころを紙の袋に入れてその紙袋を破いても、石ころは互いにくっつき合ったままぼそっと落ちる。つまり「ビー玉人間」は互いに支え合うこともできないからバラバラに生きていると言えるし、助け合うための“手も足もない”ので何かあっても互いに助け合うこともできないと言うように説明してきた。
これをいまの学校に当てはめて考えるといまの学校問題が見えてくる。支え合う子を育てていないという一言に尽きよう。「圧力」にしっかりと対峙できるだけの「自己主張できるだけのこころに育っているか否か」に問題があり、つるつるで丸くてぴかぴかした「ビー玉人間」を育ててきた私たちの社会の問題でもある。やや極端な言辞を弄するなら、「学級崩壊」も「いじめ」も「自殺」も根っこは同じといえようか。つまりそこからは「S/S/K/K」を求めない社会づくりを根底に置く大きな思想転換が必要であることがほの見えてくる
1.いま、子どもたちの問題がかしましい
2.「若者たちの自己主張を抑えてきた私たちの社会」という考えから
3.こころはどう育つのか
4.なぜこころがうまく育たなくなったか