![]()
|
No.2 不登校問題の現状と教育課題としての新たな取り組み
|
東京学芸大学教授 小林正幸
イラスト 武井佐知子
2.不登校の現状
図1、図2は、「長期欠席」と「不登校」の出現率を示すものである。「不登校出現率」に関連しては、小林(1994)が「学校ぎらい」の出現率を根拠に、中学生で1980年度から、小学生で1985年度から上昇を開始したことを示し、その後上昇の一途を辿ったことを示した。途中で年間欠席日数の基準が変化したものの、この上昇傾向は、小学生で平成10年度(1998年度)、中学生で平成13年度(2001年度)まで上昇し続けたと推測できよう。すなわち、小学生で13年間、中学生で21年間に及ぶ長期の右肩上がりの上昇が継続してきたことになる。特に、中学生において、平成3年度からの10年間の上昇は急激で、「不登校出現率」は3倍近く、「長期欠席出現率」でも2倍に至っている。
その後、学校基本調査上の「不登校」に関しては、平成14年度(2003年度)に不登校児童・生徒数の減少が報道されて以来、不登校問題は、社会問題として注目される機会が少なくなっている。しかしながら、不登校児童生徒は、教育問題や社会問題として認知されるに相応しくないほどに、問題が見られなくなったわけではない。
最近では、「長期欠席出現率」「不登校出現率」は、「学力問題」が教育課題として取り上げられた平成17年度(2005年度)から中学で再上昇し、平成19年度には過去での最高値を示し、この問題が依然として深刻である。また、この学力低下論議が社会問題としては下火になったのに呼応して、ここ数年下降し始めていたことも興味深い。
さて、「長期欠席出現率」「不登校出現率」の上昇は、とくに中学校において著しく、小学校の出現率に比べ、中学校の出現率の割合が上昇し続けている。このため、中学校の出現率を小学校の出現率で除すると、平成21年度に、長期欠席で4.79倍と過去最高の倍率を示し、「不登校」では、平成21年度に、9.04倍と過去最高の倍率を示している。この格差を「小中ギャップ」と呼ぶが、この小中ギャップは実に深刻であると言えよう。
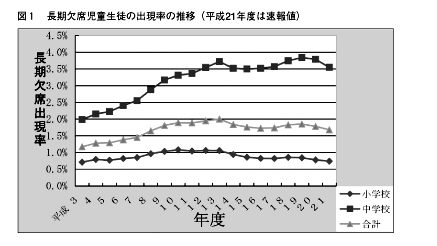
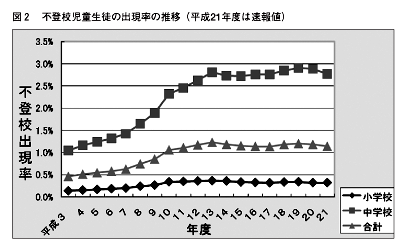
1.不登校とは
2.不登校の現状
3.不登校問題の解消に必要な予防の発想
4.教育委員会単位や学校単位での不登校対策とその成果