![]()
|
No.2 不登校問題の現状と教育課題としての新たな取り組み
|
東京学芸大学教授 小林正幸
イラスト 武井佐知子
4.教育委員会単位や学校単位での不登校対策とその成果
不登校の未然防止と早期発見・早期対応の予防レベルに着眼し、教師の関わりに対する専門家のコンサルテーションで不登校を劇的に減少させた実践がある。そのいくつかに言及しよう。これは、2002年度から熊谷市教育委員会で行われたものが最初である。この実践は、「月3日の欠席管理」「教師のチームによる登校支援」「専門家による紙上コンサルテーション」「小中連携申し送り個票」からなる。熊谷市の専門家の紙上コンサルテーションでは、累積10日を超えた児童・生徒について、教師がシートに必要事項を記載したものに、専門家が支援方法を記載したコメントを書き、それを教師にフィードバックしていくものである。その結果、年間30日以上欠席の不登校生徒は3年間で25%減少し、また、熊谷市の総欠席日数を6000日分減少させた(小林・小野、2005)
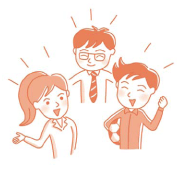 その後この実践は、「小中連携申し送り個票」の手法をメインに据え、中1ギャップを減らす取り組みとして、「小中連携支援シート」の手法へと変化をしながら劇的な成果を収めてきている。たとえば、埼玉県のある市では、5年前には、全国平均をはるかに上回る不登校出現率を示していたが、地元の保健師の学校への巡回と、小中連携支援シートの導入によって、2009年度には中学校の場合で1.8%、小学校で0.1%と、全国平均よりも1%程度低い出現率にまで低下している。一方、神奈川県南足柄市では、1年間で長期欠席者を半減させるなどの成果を示している(小林ら、2009a;早川ら、2009)。また、富山県や静岡県の特定の中学校であるが、それらの学校では、教師の努力によって、小学校よりも中学校1年、中学校1年よりも2年、2年よりも3年と、欠席者を減らしてきているのである。
その後この実践は、「小中連携申し送り個票」の手法をメインに据え、中1ギャップを減らす取り組みとして、「小中連携支援シート」の手法へと変化をしながら劇的な成果を収めてきている。たとえば、埼玉県のある市では、5年前には、全国平均をはるかに上回る不登校出現率を示していたが、地元の保健師の学校への巡回と、小中連携支援シートの導入によって、2009年度には中学校の場合で1.8%、小学校で0.1%と、全国平均よりも1%程度低い出現率にまで低下している。一方、神奈川県南足柄市では、1年間で長期欠席者を半減させるなどの成果を示している(小林ら、2009a;早川ら、2009)。また、富山県や静岡県の特定の中学校であるが、それらの学校では、教師の努力によって、小学校よりも中学校1年、中学校1年よりも2年、2年よりも3年と、欠席者を減らしてきているのである。
以上の成果からすれば、不登校問題の解消のためには、教師の不登校の子どもへの支援が大きく関連し、教師の不登校児童生徒への支援方法や態度に関わる意識のあり方が重要であると言えよう。それを裏付けるものとして小林ら(2006)は、熊谷市の不登校対策の評価に関わって、全市の教職員を対象とした意識調査を実施している。その中で、不登校への意識の高さと、不登校事例の改善の程度を比較した。その結果、対象事例の改善が顕著であった教師と、3年間に一度も不登校児童生徒を担当しなかった教師ほど、「受容的な対応」と命名された支援志向性の意識が高いことが明らかになっている。つまり、子どもに受容的に関わろうとする教師ほど、不登校を改善できるだけではなく、不登校の児童生徒を生み出さないのである。
本稿で述べてきたように、教師の子どもへの支援に関わる意識が、不登校の未然防止においても、不登校の解消においても、極めて重要な要因であることが明らかになっている。その意味で、教師の力を引き出すような支援に長けた専門家が、学校や教育委員会に関わるのならば、不登校問題は今よりもスムーズに減少していくに相違ない。

1.不登校とは
2.不登校の現状
3.不登校問題の解消に必要な予防の発想
4.教育委員会単位や学校単位での不登校対策とその成果