![]()
|
No.2 不登校問題の現状と教育課題としての新たな取り組み
|
東京学芸大学教授 小林正幸
イラスト 武井佐知子
3.不登校問題の解消に必要な予防の発想
さて、不登校は、学校不適応の一種である。学校不適応は、子どもが学校教育に合わないことである。それは、学校教育が子どもに合わないことでもある。その意味で、「不登校出現率」は、学校教育の子どもへの不適合を示す一つの現れ、指標であると言えよう。そのように考えると、小学校教育は、平成13年まで子どもに適合しない教育を行ってきたことになる。そして、中学校教育の子どもへの合わなさは依然として深刻であると言えよう。また、小中ギャップが深刻であることは、小学校教育に比べて中学校教育が、子どもに対してより適合性を失っていると考えることもできる。そして、そのことは小学校の教育システムと、中学校の教育システムへの移行に乖離が生じており、その環境の変化に子どもたちが適応しきれていない様を示していると考えることもできよう。この点に関連しては、国立教育政策研究所(2003、2005)が、小学校高学年の時期に一定程度欠席の見られた児童の中学で不登校になりやすい傾向を示し、改善策を提案しているが、その後のギャップの広がりへの歯止めにはなっていない。
一方、不登校問題の特徴として、一度不登校の状態になると問題の解決に時間を要することも強調される必要があろう。このことは、不登校問題の形成メカニズムと、問題の維持・悪化のメカニズムがあり、両者の質が異なることに由来すると筆者は考えている。そのメカニズムの詳細は別に譲るが(小林、2003)、不登校問題の解消のためには、新たな不登校を生じさせない対策が必要であり、専門家を必要とする段階は、すでに手遅れと言える状態なのである。
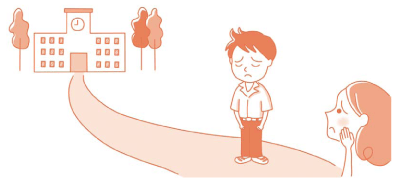
つまり、不登校の未然予防と早期発見、早期対応のレベルでの工夫がなされ、それが奏功しない限り、総数としての不登校は減少していくとは思われないのである。一人の子どもが回復するまでの期間に、2人が新たに不登校となれば、総数としての不登校は倍増する。これに対して、新たに不登校になる者がいなければ、総数としての不登校が減少する。総数が減れば、子どもに関われる学校関係者の人数が増加する。結果として、複数の学校関係者が子どもに寄り添うことができる。結果として、深刻な不登校の問題も解決しやすくなる。これは、これまで小林ら(2009b)が実践の中で明らかにしてきた知見である。
1.不登校とは
2.不登校の現状
3.不登校問題の解消に必要な予防の発想
4.教育委員会単位や学校単位での不登校対策とその成果