![]()
|
No.5 災害にさらされた子どもの心とその支援
-大人や学校はどうささえるか- |
帝京大学准教授元永拓郎
1.災害にさらされるとは
2011年3月11日は、太平洋戦争終戦後の日本において、忘れることのできない悲しい日となった。この日、突然自らの生を奪われた方も多くおられる。予想もしない突然死は、生きている者たちにとって受け入れがたい苦痛となる。まして、ご遺体が激しく損傷したり、遺体さえも見つからないならば・・、言葉もない。この日を境に、生活が一変した人も多くおられるであろう。家族や友人の喪失、町並みの喪失、住まいの喪失、仕事の喪失、ライフラインの不充分な中での避難所生活、見通しがみえない生活、これらが次々に襲ってくる。
今回はその上、原発の危機的状況も発生した。原発から立ち登る不気味な白煙を、日本のみならず世界が固唾をのんで見守った。そして原発近隣の全住民の避難、放射線への恐怖、風評被害など、被害は拡大する。被災地から遠く離れたところでも、帰宅不能、余震の恐怖、物資不足など、多くの影響が生じた。
このように今回の災害は、単一のショックな出来事の体験ではなく、さまざまな体験が次々とからみあい、そしてそれらが継続していることがわかる。つまり複合的かつ持続的に災害にさらされている体験と言うことができよう。大規模な災害ほどより複合的な体験となり、災害にさらされた人々の心理も複雑なものとなる。
そもそも災害体験は、ひとりひとりで異なったものである。その違いを意識しつつも、震災に関する模式図をざっくりと描いてみた。大地震のみでもし津波や原発事故がなければ、図1のような形になったと思う。これは阪神淡路大震災型の災害である。地震本体による家屋等の倒壊と火災、人命の喪失、避難所生活のストレスといった体験となる。これだけでもすさまじい世界である。
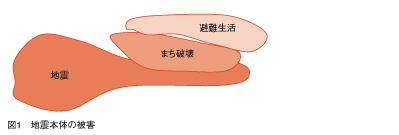
今回の災害では、地震本体に加え、津波、原発事故が加わった。阪神淡路大震災でみられた火災被害もあったが、加えて津波による甚大な被害が発生した。そして喪失体験が、人命が失われたばかりか遺体さえみつからない、根こそぎ財産がなくなったなど、これまでにないものになっている。これらのことは、とても図にできるようなものではないと思いつつも、図2に参考として示してみた。この図を見るだけでも、今回の震災がいかに複合的な影響を私たちに及ぼしているか感じることができるであろう。
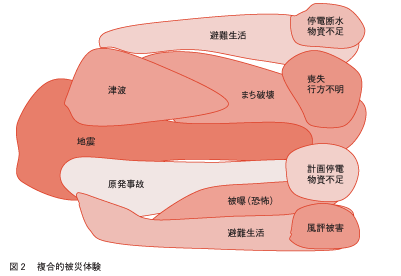
1.災害にさらされるとは
2.災害にさらされた子どもの心理
3.子どもにどうかかわるか
4.学校のかかわり