![]()
|
No.12 ポストコロナ社会のメンタルヘルス |
太刀川 弘和 Hirokazu Tachikawa
筑波大学医学医療系臨床医学域災害・地域精神医学
【〒305-8575 茨城県つくば市天王台1-1-1】
Department of Disaster and Community Psychiatry, Division of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Tsukuba,
1-1-1 Tennoudai, Tsukuba City, Ibaraki 305-8575, Japan
3.ポストコロナ社会のメンタルヘルス
2023年5月にCOVID-19が5類感染症となってから約1年になる。この間、ここまで述べてきたコロナ禍のメンタルヘルス問題はどのように変化しただろうか。前章で示すように、1)感染に直接関連する問題、2)感染対策に関連する問題、3)感染拡大(疫病災害)に関連する問題の3つにわけて考えてみよう。
まず、コロナ感染に直接関連して人々に生じた恐怖や不安は、感染による死亡率や重症度が低下したことから、徐々に低減したといえるだろう。JACSIS研究の縦断データを用いた筆者らの分析7)でも、自分や家族の感染が軽い場合の恐怖はそうでない場合に比べて低下すること、コロナ恐怖の重症度は時間依存性に低下してきたことを示している。ただし、コロナ罹患後症状(long COVID)は、いまだに持続する症状に苦しんでいる人がおり、そのうち一定数は意欲減退、抑うつ、ブレインフォグといった精神神経症状が持続する。罹患後症状の原因や有効な標準的治療法は確立していない。つまり、コロナ感染の直接症状は緩和されたが、罹患後の後遺障害が残る人たちがいる。
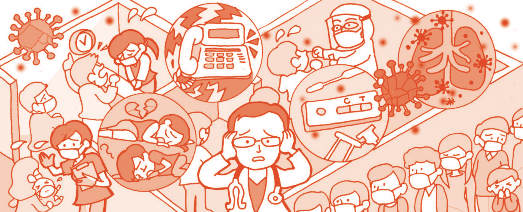
次に、感染対策(非常事態宣言、マスク着用、ソーシャルディスタンス)の影響はどうだろうか。感染対策によって生じた社会の物理的な分断や、コミュニケーションの自粛は、5類変更後になくなり、むしろ穴埋めをするかのように世界中の人々が盛んに外出するようになった。旅行業はインバウンド景気となり、学会も含めて様々な集会は対面を復活させた。コロナ禍で普及したオンラインワークが続いている企業や組織もあり、コロナ前に比して人々のコミュニケーションはハイブリッド化したといえるかもしれない。しかし、感染対策が一要因とされる、孤立・孤独の問題は続いており、不登校は著増し、2022年に政府が行った調査からの試算では日本で推計146万人がひきこもり状態にあるとされた8)。コロナ禍の自殺の背景要因の一つとされる孤独感を感じる人の割合は、2021年に36.4%に至ったが、われわれの縦断調査ではその後孤立感は減っても孤独感はあまり改善していない(データ未発表)。昨年度の自殺者数は大きく減った一方で未成年、こどもの自殺者数は過去最高を記録した。まとめると、感染対策を契機とする孤立・孤独・自殺の問題はひき続いている。
最後に、感染症災害がもたらした社会問題はどうだろう。SNSでは連日のように誹謗・中傷や偏向情報が生じ、米国、ロシアをはじめ、大国は身勝手な保護主義や戦争に走り、国際協調は過去のものとなりつつある。SDGsの理想はむなしく多様性を公然と否定する発言が国を代表する人から生じる。この寂しい社会が到来した背景に、コロナ禍で生じた情報伝染(インフォデミック)による分断と偏見・差別・デマの影響は明らかであろう。

1.はじめに
2.コロナ禍で生じたメンタルヘルスの諸問題
3.ポストコロナ社会のメンタルヘルス
4.コロナ禍は終わったのか