![]()
|
No.2 家族のコミュニケーション
|
大正大学教授 村瀬 嘉代子
聴くということ
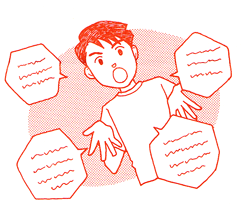 コミュニケーションの基本は、受け取ろうとする姿勢、聴く、ということです。「伝えられたものを伝えられたものとして受け止めるのは教養である」とは、文豪ゲーテの言葉ですが、近年、私どもは自己表現に力点を強調しすぎて、聴くことをおろそかにしてきたきらいがあるのではないでしょうか。かつて私は、過去にはさまざまな精神的問題を抱えて少ない人でも十ヵ所以上の医療・相談機関を訪れて、ようやく自分の生きる方向をつかみ、この世に居場所を見いだして立ち直りつつある青年期の人々に、何が立ち直る支えになったか、という主旨の調査をしたことがあります。彼らは異口同音に「聴き入ってくれる人との出会い」を挙げました。さらに、私は子どもたちが抱く父母や家族のイメージについて1989年と2001年の二回、ほぼ十年の間隔をおいて、都内の同一地区で小中学生、および長期に小児科に入院している慢性疾患の患児達に追跡個別面接調査をしたことがあります。
コミュニケーションの基本は、受け取ろうとする姿勢、聴く、ということです。「伝えられたものを伝えられたものとして受け止めるのは教養である」とは、文豪ゲーテの言葉ですが、近年、私どもは自己表現に力点を強調しすぎて、聴くことをおろそかにしてきたきらいがあるのではないでしょうか。かつて私は、過去にはさまざまな精神的問題を抱えて少ない人でも十ヵ所以上の医療・相談機関を訪れて、ようやく自分の生きる方向をつかみ、この世に居場所を見いだして立ち直りつつある青年期の人々に、何が立ち直る支えになったか、という主旨の調査をしたことがあります。彼らは異口同音に「聴き入ってくれる人との出会い」を挙げました。さらに、私は子どもたちが抱く父母や家族のイメージについて1989年と2001年の二回、ほぼ十年の間隔をおいて、都内の同一地区で小中学生、および長期に小児科に入院している慢性疾患の患児達に追跡個別面接調査をしたことがあります。
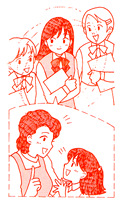 調査の結果も意味あるものでしたが、子どもたちが予想以上に「聴いて貰うこと」を欲しており、虚心に耳を傾ける聴き手に出会うと、どの子どもも真剣に考え、自分の言葉でそれを語ろうとしたことに私は感動しました。騒々しい、授業が成り立たない、と往々にして言われる彼らとは思われない素直さでした。「こんなにマジメに聴いて貰ったことは、家でも他でもない」「こうやって聴いて貰うと考え深くなる」「子どもの意見をきこうとすることはいいことだ」と言うような感想が多くきかれました。しかも印象的であったことは、ひとり二十数分くらいの面接の間に、語りながら子ども自身が考えるという表情になり、気づきをするという場面が少なからず生じたことでした。昨今、あらゆる場面で私語が多く、人の話をきかない状況が見られますが、自分の伝えようとすることには他者から聴き入って貰う、という経験を十分に持ててはじめて、人は長じてから、他者の話を聴けるようになるのだと思います。そういう意味では、家族の生活の中で、乳児が発する喃語を大切に受け止められる経験、幼児がその語りに新鮮な感動をもって真剣に聴き入って貰う経験を持つことは、単に家族内の人間関係の疎通がよくなる、というような次元に止まらず、人格の中核を形成する、という大切な意味をもつことでもあります。「よい聴き手」であるかを自問することがまず何よりも大切だといえましょう。
調査の結果も意味あるものでしたが、子どもたちが予想以上に「聴いて貰うこと」を欲しており、虚心に耳を傾ける聴き手に出会うと、どの子どもも真剣に考え、自分の言葉でそれを語ろうとしたことに私は感動しました。騒々しい、授業が成り立たない、と往々にして言われる彼らとは思われない素直さでした。「こんなにマジメに聴いて貰ったことは、家でも他でもない」「こうやって聴いて貰うと考え深くなる」「子どもの意見をきこうとすることはいいことだ」と言うような感想が多くきかれました。しかも印象的であったことは、ひとり二十数分くらいの面接の間に、語りながら子ども自身が考えるという表情になり、気づきをするという場面が少なからず生じたことでした。昨今、あらゆる場面で私語が多く、人の話をきかない状況が見られますが、自分の伝えようとすることには他者から聴き入って貰う、という経験を十分に持ててはじめて、人は長じてから、他者の話を聴けるようになるのだと思います。そういう意味では、家族の生活の中で、乳児が発する喃語を大切に受け止められる経験、幼児がその語りに新鮮な感動をもって真剣に聴き入って貰う経験を持つことは、単に家族内の人間関係の疎通がよくなる、というような次元に止まらず、人格の中核を形成する、という大切な意味をもつことでもあります。「よい聴き手」であるかを自問することがまず何よりも大切だといえましょう。
はじめに
家族生活の持つ難しさ
聴くということ
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーション
家族生活は創造の場