![]()
|
No.2 家族のコミュニケーション
|
大正大学教授 村瀬 嘉代子
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーション
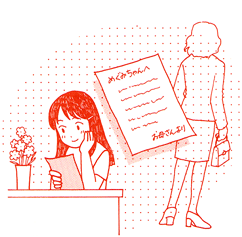 よい聴き手に次いで大切なのは、面倒がらずに「伝える努力をすること」です。少し以前のことですが、「男は黙ってサッポロビール」というキャッチコピーがヒットしました。かつては、以心伝心、黙っていても察する、という態度がわが国の文化では重んじられていました。だが、やはり伝える努力なしにはコミュニケーションは成りたちません。さまざまな問題で来談されるクライエントの方に、朝、顔を合わせて朝の挨拶をどう交わしているか、としばしばたずねますが、何と黙ったまま、もしくは用件を言うだけ、という家族が少なくありません。同じく帰宅した家族を迎える言葉や、就寝時に「おやすみなさい」の言葉かけも少ないようです。挨拶のひとことに伝わるものは多いのではないでしょうか。
よい聴き手に次いで大切なのは、面倒がらずに「伝える努力をすること」です。少し以前のことですが、「男は黙ってサッポロビール」というキャッチコピーがヒットしました。かつては、以心伝心、黙っていても察する、という態度がわが国の文化では重んじられていました。だが、やはり伝える努力なしにはコミュニケーションは成りたちません。さまざまな問題で来談されるクライエントの方に、朝、顔を合わせて朝の挨拶をどう交わしているか、としばしばたずねますが、何と黙ったまま、もしくは用件を言うだけ、という家族が少なくありません。同じく帰宅した家族を迎える言葉や、就寝時に「おやすみなさい」の言葉かけも少ないようです。挨拶のひとことに伝わるものは多いのではないでしょうか。
子どもがある年齢になれば、先に帰宅して鍵を開けて家に入り留守番をするということもあります。そのようなとき、メモ紙かメモ版に何か一言、書き添えられていたらどうでしょう。なるほど今は携帯でメールが送られはします。だが、液晶画面とは違う手書きのメモや文章の行間から、それを書いた人のぬくもりや息づかいが伝わってくるのではないでしょうか。但し、そのメモの中身は判で押したように「宿題は忘れずに」「塾へ遅刻しないで」ではわびしいことです。メモを見る相手に応じて、その時々、何気ない日常の一片を扱いながら、どこか新鮮な、ときにはユーモアを含んだようなことが書けるでしょうか。こういうやりとりを通して、人の気持ちや立場に想いを巡らす姿勢がはぐくまれていくのではないでしょうか。昨今、事件が起きると「命の大切さ」「相手の身になることの大切さ」が子ども達に向かって説かれます。何も対処されないよりはよいでしょうが、惻隠の情とは、言葉だけで育つものではないと思います。
芥川龍之介のある短編小説に次のような一節があります。「一人息子を亡くした母親が息子の親友を訪れる。亡き友人を偲んで回想するその友人の語りに、その母親は一見落ち着いて耳を傾けている・・・。友人は何と冷静な、少し冷たい母親・・・、と思いかけてテーブルの下に目を向けると、母親の手はハンカチをしっかり握りしめて強く震えている・・・。友人はそれを見て母親の言葉には容易にならない深い悲しみに気付く・・・。」非言語的方法で伝えられることは時に言葉にも増して多く深いものです。
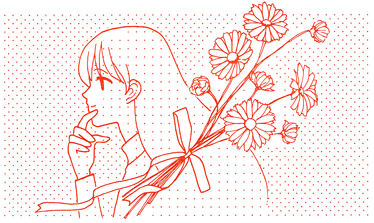
家族の生活でも、気持ちや思いは、言葉以上に振る舞いによって伝えられる場合が少なくありません。コミュニケーションとは、ただ、「言えばよい」「言ったのだから解らなくては困る」と単純にはいかないのではないでしょうか。気持ちがなぜかささくれだっているとき、理詰めのなだめ言葉よりも、おいしく入れられたお茶をそっと供されると、ふっとこころが和む場合があります。
高熱がでて食欲もなく、心許ないとき、梅干し大にかわいらしく握られて、しかも彩りよいお皿に出されるおむすびにふと手が伸びていつの間にか食事がとれ、なぜか、もうすぐ治るだろう、と気持ちが上向きになったりします。大皿に盛られたお総菜を自分が先に取り皿に分けたとき、盛られた総菜の形をさりげなく整え直して、隣へ廻す心配り・・・・、自分本位でない、人を思いやる、という姿勢はそういうやりとりを経て養われていくのでしょう。
仮に贅沢でなくとも、家庭の中のしつらえ方も無言のうちに多くを伝えるものであります。食卓に何気なく飾られた涼やかな花一輪。季節感を思い出させる食器などなど・・・・、ものやことから伝えられるメッセージは多いでしょう。
家族の生活が自然にさりげなく、しかしゆたかで確かな繋がりと和合のあるものになるには、気負わぬ、しかしきめ細やかなこころ配りのあることばと振る舞いが必要であります。
はじめに
家族生活の持つ難しさ
聴くということ
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーション
家族生活は創造の場