![]()
|
No.1 児童青年精神科と発達障害 ―自分の経験を中心にー |
日本発達障害ネットワーク・日本精神衛生会 市川宏伸
4.児童青年精神科と発達障害
1)自閉スペクトラム症
初めて児童青年精神科の病院に勤めた時、外来に来る自閉症児も病棟で診る自閉症児もほとんどは知的障害を伴うものであった。男子の障害児病棟には、床暖のあるデイルームで裸になっている自閉症者がいた。自分で衣服も着れず、食事もとれず、トイレにも行けなかった。彼らは、1943年にレオ・カナーが報告した自閉症概念から生じた、いわゆる心因論に基づく対応をされた者であった。「親の愛情が足りないから自閉症になった」と言われ、母親がひたすらおんぶし、抱っこし、何一つ自立のための躾をせずに育てた結果であった。私が病院に勤めた頃には、このような自閉症者の存在を理由に、心因論は臨床的には否定されていた。
英国の自閉症研究者であったローナ・ウィングらが1970年代に、自閉症のスペクトラム概念を報告した。1943年にレオ・カナーが報告した自閉症と1944年にハンス・アスペルガーが報告した自閉性精神病質は連続体(スペクトラム)であるとした。この考え方は、1992年に発刊されたICD-10の中に反映されており、その後日本でもアスペルガー症候群と言う言葉が知られるようになった。梅ヶ丘病院でも、平成10年前後から知的障害を伴わない自閉症児が外来を訪れるようになってきた。(図1)
図1:梅ヶ丘病院紀要より筆者が改変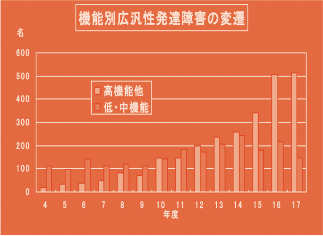
知的障害を伴わない自閉症児が増えたのではなく、医療機関に訪れる意味があると保護者が考え始めたからだと思われ、その後も外来受診者は知的障害のない者の方が多い。現在、自閉スペクトラム症を適応症とした薬剤は販売されていないが、6~18才の自閉症児の易怒性を対象とした薬として、アリピプラゾール(エビリファイ)、リスペリドン(リスパダール)の2種が認可されている。
2)注意欠如多動症
20世紀初めには、いわゆる多動児に落ち着きがないのは、道徳的な問題と考えられていたが、1920年代に世界的に流行した脳炎の後に〝落ち着きのない〟子どもが増えたことから、道徳的な問題と言う考え方は否定された。一方で1930年代後半には、覚醒作用のある薬物が〝多動児〟に有効であることが知られ、逆説的効果とされた。筆者が梅ヶ丘病院に勤務した頃は、MBD(Minimal brain dysfunction, Minimal brain damage)と呼ばれ、入院となる者は少なかったが、外来には一定の割合で来院していた。国内では認められていなかったが、米国ではメチルフェ二デートが有効であることが知られていた。筆者もメチルフェ二デートを投与し、一定の効果がみられており、学会に報告しようとしたが、当時、薬を販売していた会社から警告を受け中止した。米国では使用されていたので、おそらく、覚醒作用を懸念したからであろうと思われた。しかし平成19年12月に徐放性メチルフェニデート(コンサータ)が認可され、その後アトモキセチン(ストラテラ)、グアンファシン(ビバンセ:6~18才)、リスデキストラアンフェタミン(ビバンセ)の4種類の薬物がADHDへの適用を認められた。同時に覚醒作用があるという理由で、徐放性メチルフェ二デートとリスデキストラアンフェタミンについては、流通規制があり、医師、薬剤師、服薬者は登録制になっている。
5.終わりに
かっては、自閉スペクトラム症児と言うと、知的障害を持つ者が圧倒的であり、「自閉症児は養護学校(特別支援学校)に通う」と考えられていたが、現在は特別支援学級や通常学級に通っている者もいる。一方で、昭和20年代に制定された学校教育法には、知的障害はあっても、発達障害という概念はないため、特別支援学校高等部では職業科を中心に、知的障害のない生徒が知的障害高等部に在籍せざるを得なくなっている。医療の方では、DSM-5やICD-11の刊行により、神経発達症の中に、知的障害も自閉スペクトラム症も、注意欠如多動症も含まれている。(表2)
表2:神経発達症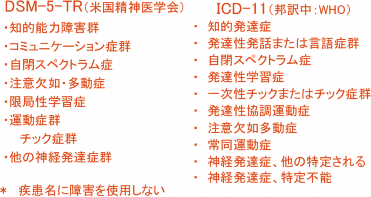
行政的には、平成17年より発達障害者支援法が施行され、国を挙げて支援が行われるようになった。この法律の制定には、文部科学省も関与しており、平成19年から特別支援教育が始まった。これに先立って文部省では、平成4年から7年間、学習障害に関する検討会が行われ、いわゆる学習障害(learning disability)と学習障害(learning disorder)の擦り合わせが行われた。この結果、教育現場にも注意欠如多動症概念が導入されるようになった。
1.子どもの精神科との出会い
2.児童精神科病院への勤務
3.知的障害児施設への勤務
4.児童青年精神科と発達障害/5.終わりに