![]()
|
No.7 IT企業とメンタルヘルス
〜メンタルヘルス指針の解説と取り組み事例〜 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 健康支援室森田美保子
イラスト 平塚 敬子
IT企業のメンタルヘルス取り組み事例について
メンタルヘルスに関する問題が毎年深刻化する中、厚生労働省は平成12年の「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を見直し、平成18年に「労働者の心の健康保持増進のための指針」を定めました。この中で、メンタルヘルスケアは「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要と謳われています。
弊社のメンタルヘルスに関する取り組みについて、その指針とそれに関連がある「過重労働による健康障害防止のための総合対策」、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を解説しながらご紹介致します。
1)セルフケアとラインによるケア
セルフケアとは、事業者が労働者にセルフケアに関する教育研修や情報提供を行い、労働者自身はストレスや心の健康について理解をし、自らのストレスの対処行動をしていく必要があります。ラインによるケアとは、事業者が管理監督者にラインのケアに関する教育研修や情報提供をし、労働者と日頃接する管理監督者が、職場環境等の改善や労働者の対する相談対応を行います。
弊社は、社内報やストレスチェックe-Learningを通じて、心身の健康管理についてのアドバイスや健康相談窓口紹介等の情報提供を定期的に行っています。また、新入社員や管理監督者を対象に、メンタルヘルスに関する健康教育を実施し、その知識の理解や予防、対処法等についての研修の機会を設けています。これらを毎年継続することによって、心の健康に関しての認識を深めていくように取り組んでいます。
2)事業場内産業保健スタッフによるケア
事業場内産業保健スタッフ等によるケアとは、メンタルヘルスを行うために事業場内に必要な人材(産業医、看護職、人事労務、衛生管理者等)を確保し、心の健康づくりの推進や労働者や管理監督者を支援します。
弊社の産業保健スタッフは、健康支援室の中では産業医、産業看護師、事務スタッフになります。人事労務部門では、衛生管理者がおり、お互いがうまく連携を取りながら、日々の産業保健活動を行っています。産業医は、メンタルヘルス研修や健康相談、健診の事後措置等、一次予防から三次予防まで全てに関わりを持ち、幅広い活動を行っています。人事労務担当者は、管理監督者から部下の労務管理に関する相談について対応しています。産業看護師は、役割的に従業員と直接かつ対等にコミュニケーションをとることのできる特性を生かし、毎年健康診断時に従業員と個別面談を行っています。健診の問診に対するアドバイスや禁煙、節酒などの動機付け支援、健康支援室や外部の相談機関の紹介等を行い、これらを継続することで健康支援室を身近に感じ、早期に相談しやすい関係づくりに努めています。
もし、事業場内産業保健スタッフに常勤の産業医や看護職がいない場合は、人事労務担当者や衛生管理者が厚生労働省の指針やメンタルヘルスに関する知識を学びながら、嘱託産業医と連携をとり、各々の立場で協力しながら適切な対応を図っていくことが大切です。
3)事業場外資源によるケア
事業場外資源によるケアとは、従業員やその家族が事業場外資源を用いて早期に心の相談や支援を受けることができるように推進するケアです。
弊社では、外部の健康相談として数年前からEAP(従業員支援プログラム)を利用しています。弊社の業種においては、問題を抱える従業員が増えることが予想され、本社にある健康支援室を利用しにくい地方拠点勤務者や、会社に知られたくない悩みを抱える従業員のために、自分のパソコンや携帯電話からいつでも相談できる外部の相談機関を設けました。定期的にイントラネットや社内報でEAPをPRすることでその存在を知る人が多くなり、EAPの精神科医や臨床心理士に相談し、心の病による休業を防止することができたケースが徐々に増えてきています。事業場内の産業保健スタッフだけでは限界がある場合EAPの活用をお勧めしますが、さまざまな特徴を生かしたEAP機関がありますので、その選択にあたっては企業のニーズにあった対応が期待できる機関かどうか十分に検討する必要があります。
この他の事業場外資源には、従業員が加入している健康保険組合の契約相談機関(外部委託の場合)、労災病院勤労者メンタルヘルスセンター、保健所、精神保健福祉センターなどがありますので、必要に応じて従業員に紹介してみてはいかがでしょう。
4)その他
(1)過重労働による健康障害防止対策
脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされています。この面接指導の対象者は、一定の長時間労働(1週40時間を超える労働時間が1ヶ月当たり100時間超の時間外・休日労働)を行い、かつ疲労の蓄積が認められる者(本人の申し出による)です。面接指導とは、疲労蓄積に関する問診や健康診断結果を参考に心身の状況を確認する面接指導を行いますが、面接結果によっては就業上の措置を講じなければなりません。
弊社では、職場に対する残業削減対策、労働時間管理の徹底と同時に、健康障害防止策としてある基準以上の長時間労働者は必ず面接指導を受けることにしています。面接は、厚生労働省が作成した「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を使用し、業務状況や睡眠時間、健康診断結果、現病歴、既往歴、生活習慣(喫煙、飲酒)についての問診や血圧測定を行っています。対象者へはセルフケアの指導、職場へは事後措置としての指導・勧告(就業時間制限、年休取得促進等)を行っています。
(2)職場復帰支援
平成16年に「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」が厚生労働省から発表されました。メンタルヘルス対策は、一次予防(早期予防)、二次予防(早期発見・早期対応)に加え、三次予防(治療・復帰・再発防止)として、円滑な復帰支援を目的に下記のステップが示されていますが、各々の事業場の実態に即した復帰支援プログラムを組織的に策定して取り組むことが重要です。また、休業前や休業中から本人の状態を把握しておくことで、復帰可否の参考、再発予防につながることがあります。職場復帰支援は、復帰時に始めるのではなく、休業の診断書が出た時点から下記のステップに従って開始することが望ましいでしょう。
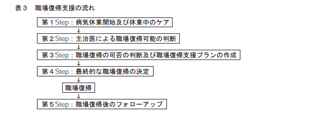
弊社は、この5つのステップに基づいた復帰支援プログラムを計画し、長期的な支援を行っています。
<第1Step:病気休業開始及び休業中のケア>
原則、休業前に面談を行い、産業医が休業に至った経過を確認します。人事労務担当者は、雇用の安定と金銭面の不安軽減のために就業規則(休業制度、休業中の補償・連絡方法等)や職場復帰支援について説明をします。休業中は、1ヶ月に1回程度、健康支援室へ来室してもらい、産業医が状態の確認と必要に応じたケアを行っています。
<第2Step:主治医による職場復帰可能の判断>
主治医からの復帰可能の診断により、「復職前面談」を実施します。次のステップである「復職判定面談」まで生活リズムの安定を促す指導を行い、図書館通いや行動日誌の記載等を提案します。日誌をつけることは自分自身の状態について振り返ることもでき、復帰判定の参考にすることができます。
<第3Step:職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成>
職場復帰の可否について、従業員と管理監督者、産業医、人事労務担当者で「復職判定面談」を行います。体調と行動日誌の内容を確認しますが、毎日通勤できるような生活リズムが整っていない場合は復帰を延期させることがあります。
<第4Step:最終的な職場復帰の決定>
従業員の健康状態を確認した上で、産業医による職場復帰支援に関する意見書が作成され、その意見に基づき事業者による最終的な職場復帰が決定されます。
<第5Step:職場復帰後のフォローアップ>
弊社では、職場復帰後のフォローアップは6ヶ月間とし、月に1回従業員と管理監督者、産業医、人事労務担当者で面談を行い、業務遂行状況の確認や翌月の勤務時間、業務量等の決定を行っています。システムエンジニアの職場復帰後の配慮については、短時間勤務や残業禁止等の労働時間の制限、客先常駐業務を避ける、システム開発運用のバックサポートや事務作業等を行うなどが挙げられ、それらをケースに応じて提案しています。
復職時には重要な点が2つあります。ひとつは職場側の復帰支援の体制を整えられているか、もうひとつは従業員本人が休業に至った誘引を認識し、同じことが起きた時にどう対処していくか、振り返りと対策が考えられているかです。うつ病の治療は薬と休養と言われていますが、カウンセリングや家族、友人との交流の中で、自分の性格傾向を振り返り、対処法を認識しておくことも大切です。
はじめに
なぜIT企業に心の病が多いといわれているのか?
IT企業のメンタルヘルス取り組み事例について
ご家族の対応について
まとめ