![]()
|
No.10 お年寄りに歌を!
−孤立を防ぐ− |
京都大学大学院教育学研究科教授 山中康裕
4.イメージ連句について
今度は、イメージ連句についてお話ししましょう。連句そのものは、むしろ、統合失調症の患者さんたちに恰好の方法であって、なまの人間関係そのものには大きな支障があり、なかなかうまく生きることができずらいが、ことばに独特の意味を付与したり、独特のあじわいを感ずるのに長けたことの多い彼らと、脳波を記録した用紙で不要になったものの裏側の素白の紙を用いて、筆ペンで、毎週彼らと連句を連ねておりました。そして、せっかく毎週壁に貼り出すのだったら、ちょっとアクセントに、挿絵のように絵を挟んでみようと、この横長用紙の中央あたりに、雑誌や駅などにおいてあるパンフレットなどから、美しい舞妓さんや紅傘やお花などの写真や絵をあしらってコラージュ(貼り合せ)しておりましたが、これが、連句そのもののイメージのインデューサー(誘い水)ともなったりして、なかなかの評判となったのでした。
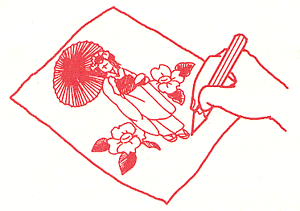 これを、高齢者病棟にも用いることにしてみました。ただし、もうのっけから分かっていたことは、そもそも、日常のことばそのものすら忘れたり、失ったりしている彼らに、五七五、七七の連句形式を維持することなどは土台不可能なことでした。しかし、でも、あのイメージ・コラージュにはとてもよく反応してくれる人たちが何人かいることが分かり、これに対して彼らが語る、言葉の断片やつぶやきでもいいから、それらの片言隻語を書きつけることにしたのです。もちろん、彼らの実名を下に付して。この彼らの実名をさらさらと目の前で書き入れるという所が、どうやら彼らの気に入るミソなのでした。それまで、自分の名前すら忘れかけていた彼らが、自分の言ったことがすぐそこに書き出され、しかも、自分の名前がそこに付されると、急にニコッと表情が和らいだり、相好を崩されたりすることに気づきました。彼らのうちには、自分の名前が書かれ、貼り出されると、それを何度も見にいく人すらあり、それまで大声で独語のように喚き散らしていた人が、自分の名前を書かれると、急に微笑んで、それに見入られ、静かになられるのでした。
これを、高齢者病棟にも用いることにしてみました。ただし、もうのっけから分かっていたことは、そもそも、日常のことばそのものすら忘れたり、失ったりしている彼らに、五七五、七七の連句形式を維持することなどは土台不可能なことでした。しかし、でも、あのイメージ・コラージュにはとてもよく反応してくれる人たちが何人かいることが分かり、これに対して彼らが語る、言葉の断片やつぶやきでもいいから、それらの片言隻語を書きつけることにしたのです。もちろん、彼らの実名を下に付して。この彼らの実名をさらさらと目の前で書き入れるという所が、どうやら彼らの気に入るミソなのでした。それまで、自分の名前すら忘れかけていた彼らが、自分の言ったことがすぐそこに書き出され、しかも、自分の名前がそこに付されると、急にニコッと表情が和らいだり、相好を崩されたりすることに気づきました。彼らのうちには、自分の名前が書かれ、貼り出されると、それを何度も見にいく人すらあり、それまで大声で独語のように喚き散らしていた人が、自分の名前を書かれると、急に微笑んで、それに見入られ、静かになられるのでした。
1.高齢者において残されている能力
2.カイロスを共有する時間
3.そもそも歌を取り入れることとなったきっかけ
4.イメージ連句について
5.ある日のイメージ連句
6.歌の連なり