![]()
|
No.11 職場のハラスメント
|
東京女子医科大学附属女性生涯健康センター 加茂登志子
イラスト 小林恵理子
2)職場におけるハラスメントの種類と定義
ここではセクシュアル・ハラスメントとパワー・ハラスメント、その周辺で使用されるいくつかの概念について俯瞰したい。
職場のセクシュアル・ハラスメントは、女性雇用者の増加に伴って顕在化してきたものであり、多くのハラスメント群のなかで最も早く平成9年の男女雇用機会均等法(以下均等法)改正時に規定が設けられた。その後、平成19年の改正では「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けることや、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること」と定義され、女性だけなく男女両方に適用されることになった。
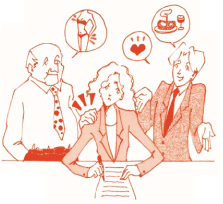 現行の均等法上のセクシュアル・ハラスメントは、「対価型」と「環境型」に2大別されており、前者は、労働者が意に反する性的な言動を拒否したことによって解雇や降格・不利益な配置転換・減給などの不利益を受けることをさし、後者は労働者の意に反する性的な言動によって、労働者の就業環境が不快なものになったために、労働者の就業意欲が低下したり、労働者が苦痛に感じて業務に専念できないなど、能力の発揮に悪影響が生じることとされている。例を挙げると、性的な冗談やからかい、食事やデートなどへの執拗な誘い、性的な事実関係を尋ねること、身体への不必要な接触、性的な噂を意図的に流すこと、わいせつな図画の配布、性的関係の強要などが挙げられる。
現行の均等法上のセクシュアル・ハラスメントは、「対価型」と「環境型」に2大別されており、前者は、労働者が意に反する性的な言動を拒否したことによって解雇や降格・不利益な配置転換・減給などの不利益を受けることをさし、後者は労働者の意に反する性的な言動によって、労働者の就業環境が不快なものになったために、労働者の就業意欲が低下したり、労働者が苦痛に感じて業務に専念できないなど、能力の発揮に悪影響が生じることとされている。例を挙げると、性的な冗談やからかい、食事やデートなどへの執拗な誘い、性的な事実関係を尋ねること、身体への不必要な接触、性的な噂を意図的に流すこと、わいせつな図画の配布、性的関係の強要などが挙げられる。
一方、パワー・ハラスメントは日本で生まれた概念であり、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること」をさす2。現在では過労死、過労自殺と並んで日本の労働問題から発生した言葉の一つとして、海外でこの言葉が用いられるようにもなった。パワー・ハラスメントはセクシュアル・ハラスメントに比べ、男性も被害に遭いやすいものであるとされ、会社のリストラのときの上司の恫喝などが例として挙げられる。亜型分類としては、パワハラの手段によって「攻撃型」、「否定型」、「強要型」、「妨害型」の4つのタイプに分けるもの2、原因に着目して「リストラ型」「職場環境型」「人間関係型」「労働強化型」「過剰競争型」「セクハラ型」の6つのタイプに分けるもの3などがある。セクシュアル・ハラスメントに比べ法整備はまだ進んでいないが、社会的な認識は高まっており、民事裁判ではパワー・ハラスメントによる労働災害を認める判例が散見されるようになってきている。
そのほか、モラル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントなどの概念がこの領域に関連して用いられやすい。モラル・ハラスメントとは、一言でいえば言葉や態度等による精神的な暴力をさす。また、提唱者であるマリー・フランス・イルゴイエンヌによれば、職場のモラル・ハラスメントとは「言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること」4であり、「職権濫用的なモラル・ハラスメント」、「状況や関係によるモラル・ハラスメント」のほか、自己愛性性格型加害者による、陰湿なやり方で相手の心を傷つける「純然たるモラル・ハラスメント」の3つに大きく分けられるという5。ジェンダー・ハラスメントは、社会的・文化的に形成された性別に基づくハラスメントをさす。男女の性別役割分担を固定的なものと考え、「女のくせに」「男のくせに」といった「らしさ」のイメージに基づく差別的な言動や行動によって、就業環境を悪化させたり退職を余儀なくさせるもので、広義のセクシュアル・ハラスメントであり、また、セクシュアル・ハラスメントを誘発する背景となるものである。その他、しばしば用いられるものにモビング(Mobbing;職場いびり)があるが、モラル・ハラスメントとほぼ同義である。
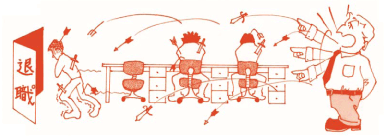
1)増えるハラスメント相談
2)職場におけるハラスメントの種類と定義
3)ハラスメントによって生じる心身の不調
4)職場のハラスメントが激増する背景と女性という存在
5)加害行為はなぜ繰り返されるのか
6)職場のハラスメントに対する対策と問題点