![]()
|
No.11 職場のハラスメント
|
東京女子医科大学附属女性生涯健康センター 加茂登志子
イラスト 小林恵理子
6)職場のハラスメントに対する対策と問題点
セクシュアル・ハラスメントにしても、パワー・ハラスメントにしても、被害者は自分の問題として抱え込まず、早い時点で第3者に相談を持ちかけていく姿勢が重要である。相談を持ちかける場所としては、職場内のハラスメント委員会、地域の労働局の労働相談、弁護士などが挙げられる。心身の不調がある場合には、医療への受診も勧めたい。また、職場管理者には予防対策として専門家による講習会を開催し、とくに中間管理者への知識普及を勧めたい。
しかし、こういったお勧めが十分に機能しているとは言い難い状況もまた一方で認識しておく必要があるだろう。セクシュアル・ハラスメントに関しては、話題となり始めてから約20年の時を経て男女雇用機会均等法等法整備にまで対策が進んだことは大きく評価されるべきことである。平成19年に改正された男女雇用機会均等法には、事業主のセクシュアル・ハラスメントに対する安全配慮義務に関しても明確に謳われている。これを受けて大企業や大学を含む学校法人等では内部で(セクシュアル)ハラスメント対策委員会を設置し、対応のフローチャートをホームページで公開しているところも珍しくなくなってきた。しかしながら、実際のケースにかかわっていると、委員会の設置は進んだものの、実際に機能するのは今後の課題であろうと思われるものが少なくない。セクシュアル・ハラスメントの概念は、性的な言動やお茶汲みの強要から職場内での性暴力被害(レイプ)ともいえるような性行為の強要まで、行為の類型も程度も多様性に富んでいる。性暴力被害ともなれば問題の是非はないが、その判定に当たって「加害側の言動や行動が相手の意に反しているかどうか」という被害側の主観の問題に重点がおかれることが多いため、分かりにくいと敬遠されることもしばしばであり、また、本来であれば犯罪であるレイプに対し「セクハラ」という表現を用いることで、その重みが軽減されてしまうこともある。あるいはいまだに職場内のセクシュアル・ハラスメント委員会に申し立てた被害者が訴えたことでかえって中傷を受けてしまうケースもある。職場におけるジェンダーの勾配は、解決プロセスにも大きな影響を与えているのではないかと考えられる。むしろ、法整備にまで至っていないパワー・ハラスメントのほうが、被害者も加害者も男性である割合が多いがゆえに、解決が早いといえるかもしれない。
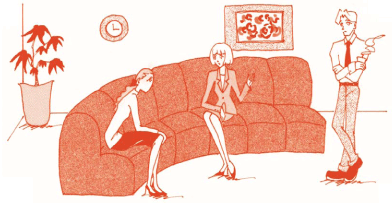
いずれにせよさまざまな被害が経験となって蓄積され、法制化につながり、それがやがて職場環境の改善をもたらしてきた表の歴史の影に、傷つき、その職場から離脱しながらも心身の不調をその後もずっと抱え、苦しんでいる集団がいることを臨床に携わるものは忘れてはならない。
────────────── 文 献──────────────
1 東京都労働局:平成19年度「労働相談及びあっせんの概要」、東京都、2008
2 岡田康子:上司と部下の深いみぞ―パワーハラスメント完全理解、紀伊国屋書店、東京、2004
3 金子雅臣:職場いじめ―あなたの上司はなぜキレる、平凡社新書、東京、2007
4 マリー・フランス・イルゴイエンヌ:モラル・ハラスメント―人を傷つけずにはいられない、紀伊國屋書店、東京、1999
5 マリー・フランス・イルゴイエンヌ:モラル・ハラスメントが人も会社もだめにする、紀伊國屋書店、東京、2003
6 岡本祐子、松下美知子編:女性のためのライフサイクル心理学.福村出版.東京,1994
1)増えるハラスメント相談
2)職場におけるハラスメントの種類と定義
3)ハラスメントによって生じる心身の不調
4)職場のハラスメントが激増する背景と女性という存在
5)加害行為はなぜ繰り返されるのか
6)職場のハラスメントに対する対策と問題点