![]()
|
No.4 見えざる自殺問題:自死遺族のサポート
|
奈良女子大学生活環境学部教授 清水 新二
「自死」という言葉
最後に、「自殺」という耳慣れた言葉に代えて、少々耳慣れない「自死」という言葉を使う理由を簡単に述べてみましょう。病死などの自然死に対して自殺という表現は、同じ人間の死であるにもかかわらずどこか自死した人を蔑むようなイメージと響きがあると感じませんか?あなたはそうでないかもしれません。しかし社会にはそうした感じ方をしている人がかなり多くいるように思います。確かに、1日でも長く行きたいと思っている人がおり、その立場から見れば、様々な事情ながらその尊い命を自ら絶ってしまうのはあまりにももったいない、不自然なことと考える人もいるのです。 あるいはもっと単純に、自死は結局その人が弱いからだとか、逃避だとか言って、蔑視、忌避する場合も少なくありません。
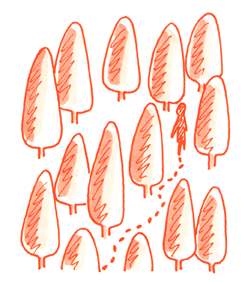 ただ言うまでもなく、誰でもむざむざと死にたくはないはずですし、死ぬことの背景にはそれぞれのっぴきならぬ事情があるでしょう。そしてある人は病死である人は自死で命を終えるのだ、と考えるしかないと私は思っています。というのは、自死により遺された遺族たちの立場に立つとき、そして遺族が出会う自死に対する社会の偏見、蔑視、忌避がどれほど辛いものであるかを想うとき、さらに大切な人を失った上にその悲しみや様々は感情を誰にも語れずに自分のこころの奥深くに封印し続けなければいけない孤独感、孤立感を想うとき、傷口に塩をもみこむようななまざしや響きを纏っている「自殺」ということばを敢えて使う必要はないと感じるからです。この点では自死遺族の希い通りの言葉遣いを優先したく考えたからです。当然にも、異なった感情や意見の方もいることでしょう。それはそれでいいと思います。
ただ言うまでもなく、誰でもむざむざと死にたくはないはずですし、死ぬことの背景にはそれぞれのっぴきならぬ事情があるでしょう。そしてある人は病死である人は自死で命を終えるのだ、と考えるしかないと私は思っています。というのは、自死により遺された遺族たちの立場に立つとき、そして遺族が出会う自死に対する社会の偏見、蔑視、忌避がどれほど辛いものであるかを想うとき、さらに大切な人を失った上にその悲しみや様々は感情を誰にも語れずに自分のこころの奥深くに封印し続けなければいけない孤独感、孤立感を想うとき、傷口に塩をもみこむようななまざしや響きを纏っている「自殺」ということばを敢えて使う必要はないと感じるからです。この点では自死遺族の希い通りの言葉遣いを優先したく考えたからです。当然にも、異なった感情や意見の方もいることでしょう。それはそれでいいと思います。
自殺者3万人時代
中高年男子の自死問題とサバイバー
4人に1人が親しい人の自死を体験
「生き残り」の意味
自死遺族へのサポート〜ポストヴェンション〜
「自死」という言葉
「自死を受けいれる」ということ